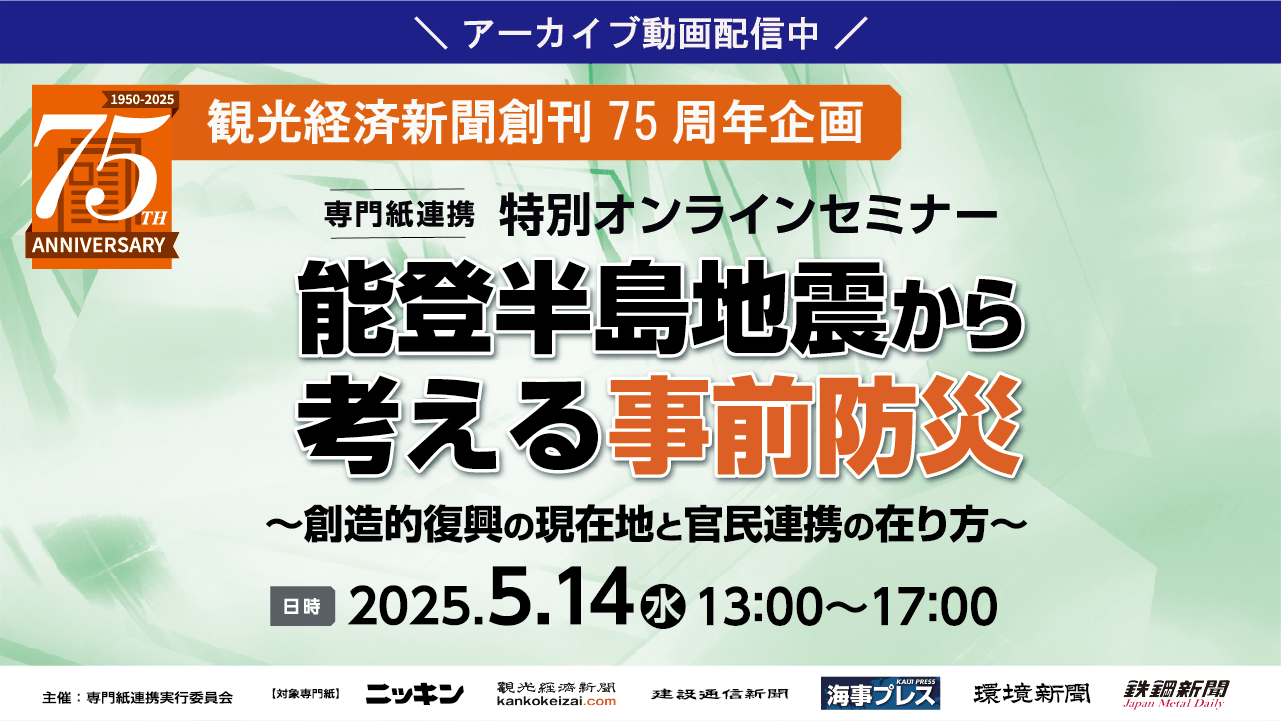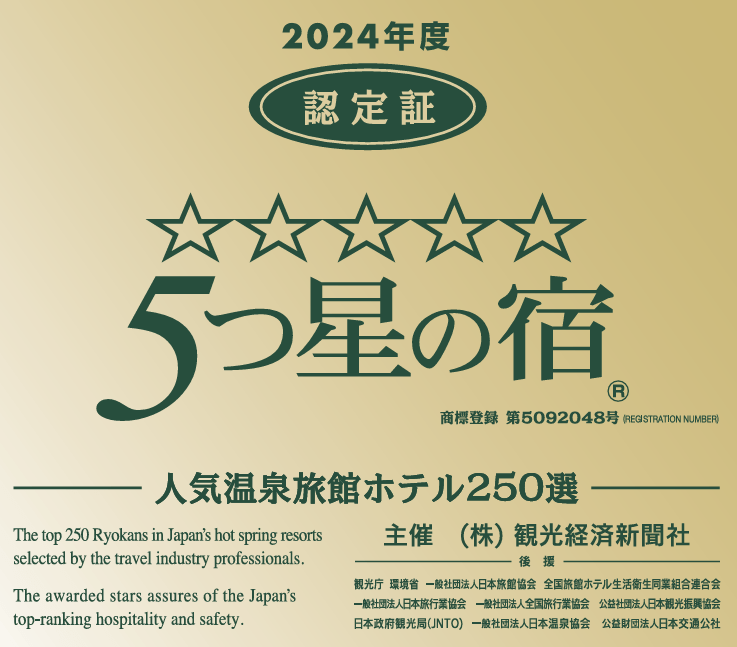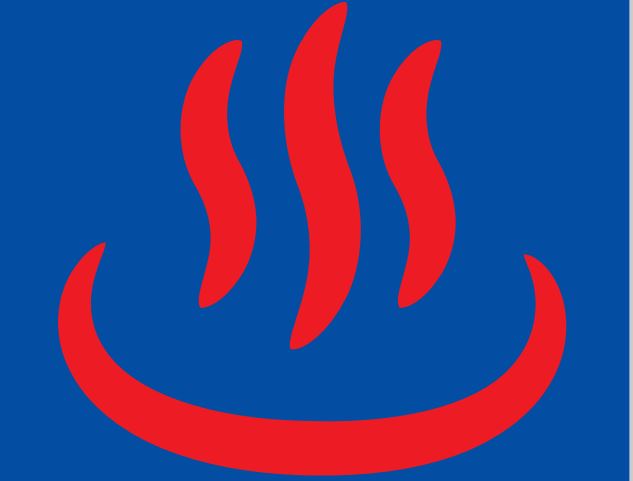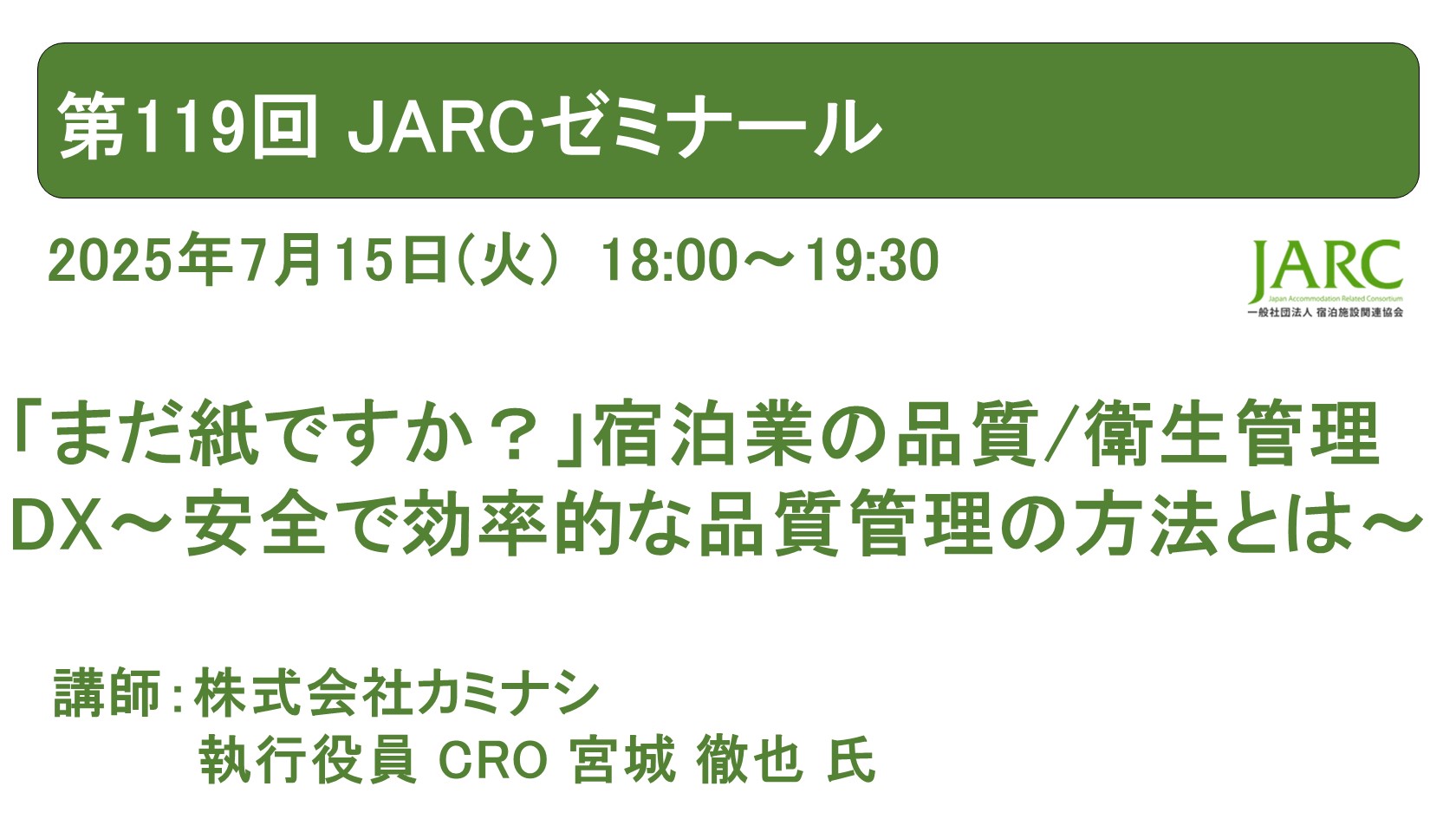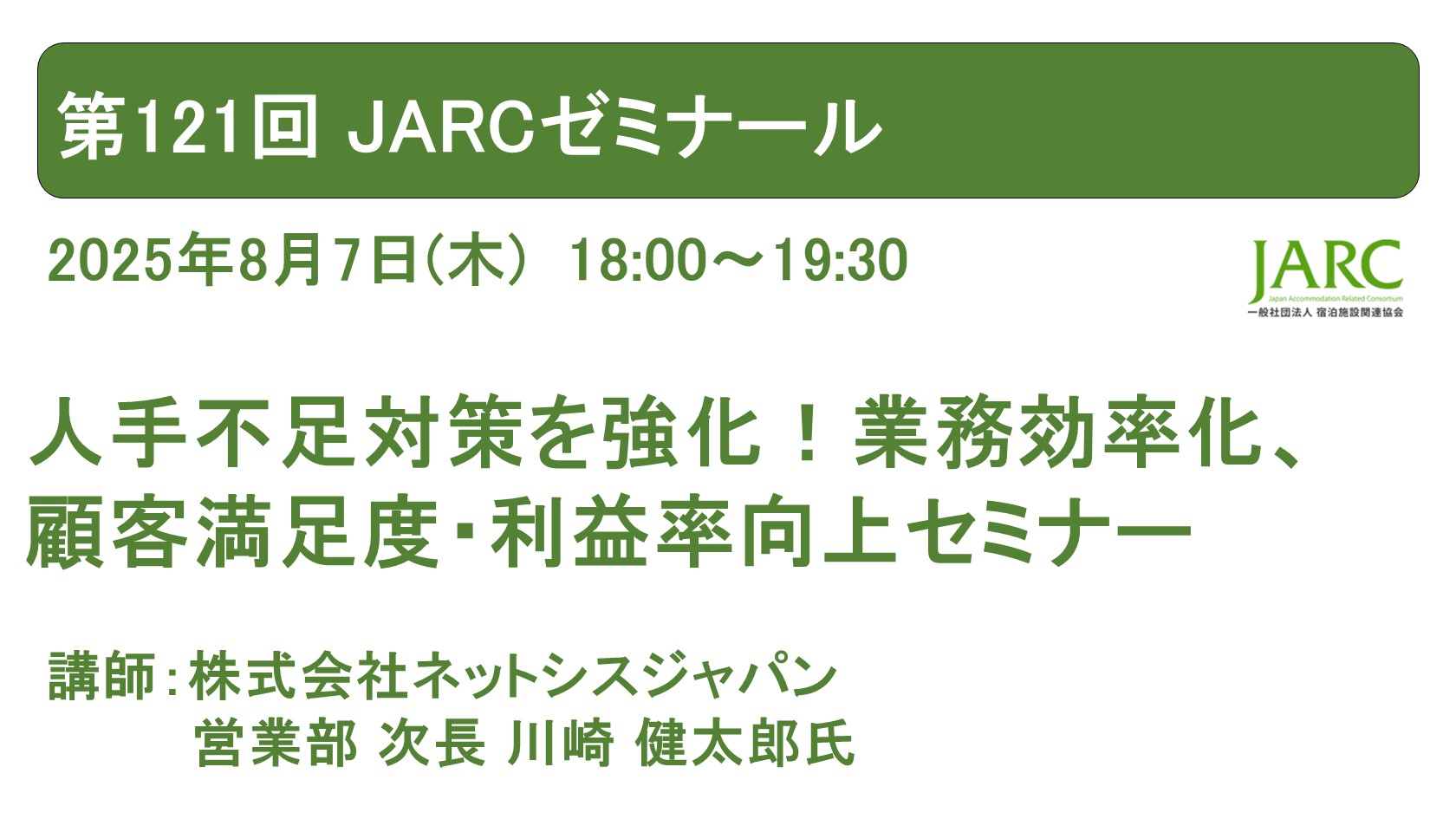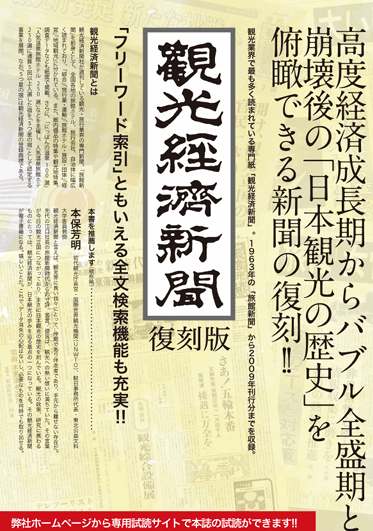古滝屋 里見社長
学習ツアーで教訓を伝える
地域の宝をもっと知ってほしい
いまだ帰還困難区が残る福島県の浜通り地方。大熊町や双葉町では帰還困難区域の面積は広い。一部解除の地域はあるものの、原発事故の汚染により徒歩、自動二輪での走行の禁止区域になって規制されている。「原子力災害考証館」を建て、震災の記憶を伝えようと奮闘するいわき湯本温泉「古滝屋(ふるたきや)」の里見喜生社長(52)にインタビューした。(2月11日取材)
――震災から10年、現在の心境は。
里見 長く感じましたね。津波、震災というのは、月日が過ぎると復旧復興が進む。原子力災害対策は進んでいるようで、原子力災害関連死というのが今も毎日、新聞に載っている。つまり、現在進行中、だから長く感じる。よく「震災はどうでしたか」と聞かれますが、地震によって一瞬にして電気、ガス、水道、固定電話に携帯電話がストップしてしまった。震災発生時の寒さは堪えた。しかし異常事態の序章の始まりに過ぎなかった。
――震災当時から現在まで、ご自身の宿や地域でどのような活動を行ってきましたか。その成果も教えてください。
里見 一つが「Fスタディツアー」と称してやっている学習ツアー。震災の教訓を伝えるガイドは、他の地域からいわき湯本温泉に来るきっかけになる。原子力被災地の富岡町などを案内するうちにその思いが強くなり、きちんとエネルギーとか電気について知ってもらう必要があると思ったのがボランティアガイドの始まりだ。
もう一つが集合住宅(体育館)などでの生活様式の違いや、高齢者、障害を持つ方々と、環境が変わると大声を出し、急に走り出す子どもに、迷惑だから出ていってくれという共同生活者間のあつれきが生じる光景をよく見かけた。暗い海の中に親子で飛び込んでしまうのではと思う時さえあった。
また、原子力災害で双葉郡全体が一時封鎖されてしまったので、そこにいる高校生のために、旅館が空っぽとなった客室を使って学生寮とした。これは福島県の教育委員会から連絡があり、寮として提供してもらえないかと連絡が入ったことがきっかけで、NPO「ふよう土2100」を立ち上げ、安心して過ごしてくださいという意味を込めてスペースを作った。
――さらなる復興に向けて、今後必要なことは。
里見 地域には復興に向けて頑張っている人は周りにたくさんいるが、個人間でも復興への思いは違う。ハード事業で奇麗に整備されることが復興ではない。心の安心感であったりとか、家族が元通りに一緒に住むことが本当の復興だと言う方もいる。地域住民がやっと前の状態に戻れたとか、前を見ることができるとか、未来を描けるようになったとか、その声をたくさん聞くことが復興だと思う。
この旅館も公民館のような役割をしようと思った。大熊町から避難された方々が、お風呂のない生活を強いられていた。当温泉の源泉は脈々と湧出していたので、マイクロバスで奥さんたちを送迎し、浴場に入っている光景を映像で流してもらった。
――10年を迎えた今、伝えたいことは何でしょうか。
里見 震災前は団体、震災後は個人客がほとんど。宿泊施設や旅行エージェントの方に共通して言えることはその土地の歴史とか文化などの地域の宝をもっと知ってもらいたいということ。
旅館というのは、原発事故が起きても、津波が起きても、都合が悪くなって移動することができない。震災はきっかけかもしれないけど、東北の歴史とか文化とか、郷土料理とか伝統芸能の東北ならではのよさにもっと目を向けてほしい。
今回のコロナで大変な時代が到来しているがプロのコーディネーターが観光地には必要だ。その結果、地元で楽しみ方のバリエーションが増える。
その効果で観光業界が動き、宿泊や飲食、お土産の購買など、地元に消費が生まれる。
2011年3月11日の翌日から1年4カ月休業した。3月中に約4千人の予約キャンセルがあったが、ネバーギブアップで取り組んできた。
温泉街の10キロほど先に小名浜港があり、ピチピチの魚介類を仕入れてお客さまに提供している。「地元の魚、野菜うめえべ」との言葉を、一時使えない時期があったが、逆に福島の郷土愛と食材へのこだわりが強くなった感がある。
【聞き手・平塚真喜雄】

里見 喜生氏(さとみ・よしお)=いわき湯本温泉「古滝屋」16代当主。東日本大震災で旅館が大きな被害を受けたが再建。旅館は継続しながら、観光業から未来づくり業へ転身。「NPO法人ふよう土2100」を設立し、障害児支援。「おてんとSUNプロジェクト」を立ち上げ、衣食住の持続可能社会に注目。「Fスタディツアー」原子力災害を考察するフィールドガイドを務める。福島県いわき市在住。