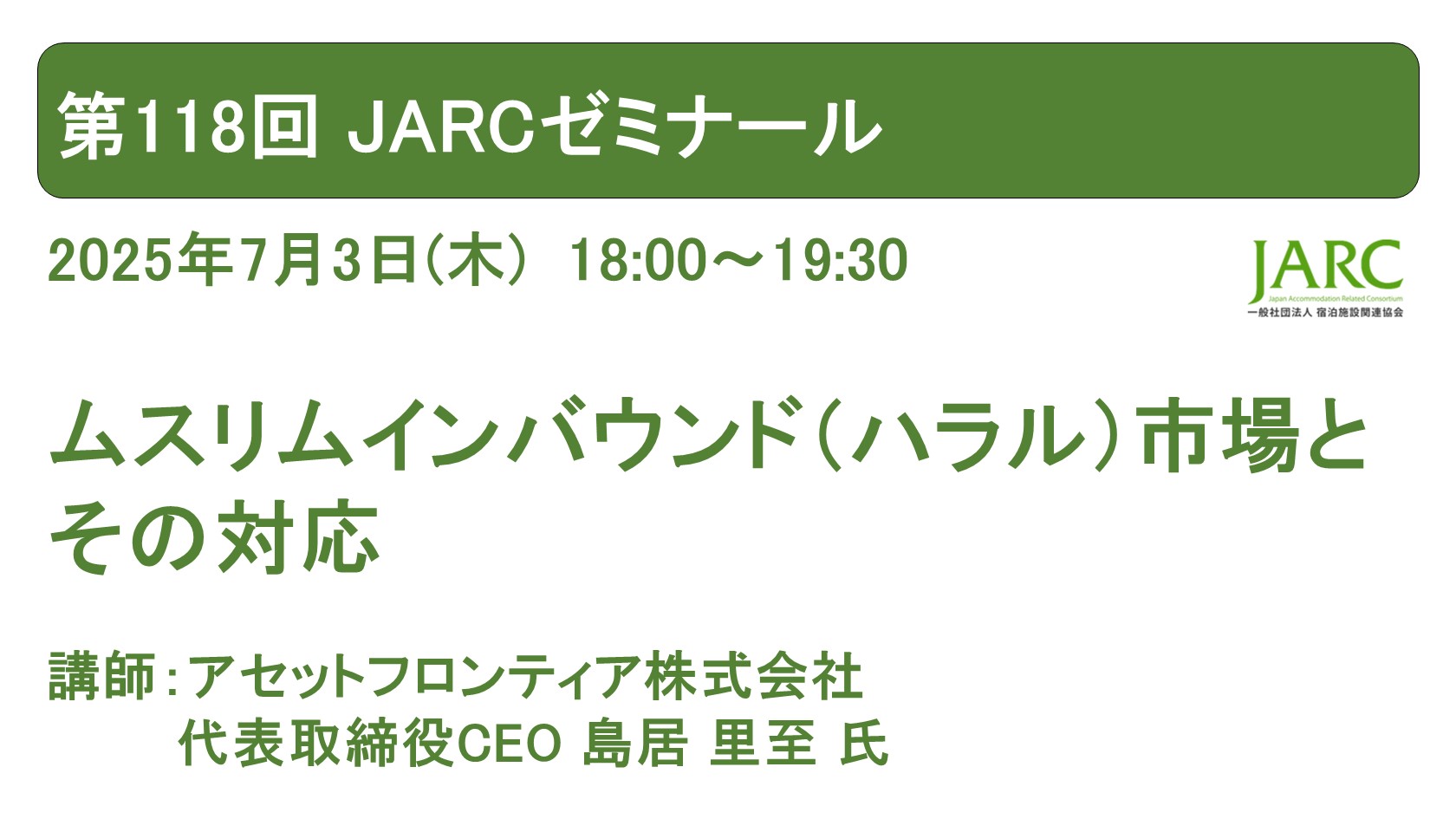日本ホテル協会会長 小林 哲也氏
新会長の取り組み方針
差がつくのは情緒的価値 人材の育成に力を入れる
──3月の春季総会で会長に就任した。組織運営で取り組むことは。
「会員の増強は継続的な課題だ。会員数は1997年に458まであったものが、2008年には200ぐらいまで落ちた。今はNHKの受信料の取りまとめや、著作権使用料の割引などによるメリットが増えたことが功を奏し、09年から現在に至るまでその数は250ぐらいまで戻り、今なお増加傾向にある。これを300、350と増やしたい。会員のメリットを創出して、いかに多くの会員に入ってもらうかを協会のみんなで知恵を出して考えなくてはいけない」
──利用客から見た協会の目指すべき姿は。
「ホテルは安全、安心、快適が重要だから、これらの業界全体のレベルを上げたい。その上で、お客さまに『ホテル協会の加盟ホテルはサービスが違うね』『また来たいね』と言ってもらえるようなサービスを目指して信頼感を得ていきたい。ホテルの要素というと普通はハードとソフトで終わるのだが、私は、ソフトからヒューマンを抜き出して、ハード、ソフト、ヒューマンの三つの要素がバランスよく高品位に整わなくてはならないと考えている」
──その三つの要素のうちで最も重要なのは。
「すべて大事で順番はない。だが、しいて言えばヒューマンだ。いくら費用をかけていいハードを造り、知恵を絞っていいソフトを作っても、それを動かすヒューマンがしっかりしていなければ生かされない。また、サービスには機能的価値と情緒的価値がある。ロビーや客室、レストランといった機能的価値は、そのお客さまの価値観に見合う快適性があるか否かの違いはあるが、ある程度のレベルまでいったらほぼ同じだ。差がつくのは情緒的価値で、それは、ヒューマンによって創出される。その意味でも、協会として人材育成を強化していきたい」
──会員ホテルの人材育成をどう支援するのか。
「各ホテルが自社の人事・研修制度を作り、改善していくための情報の交換、共有をしていきたい。ほかのホテルでいい制度があったら、それをまねることも一つの方法だ。学びの基本はまねることから始まる。まねをしているうちにオリジナリティが出てくる。ホテル協会内で、人材育成の事例を情報収集して、『こんなことができる』という提案を各ホテルに発信していくことも有効な手段だ」
───会長のホテル、帝国ホテルでの人材育成法は。
「いいサービスを行ったスタッフをみんなの前で褒めることでよい事例を共有し、本人だけでなく周囲のスタッフのモチベーションもアップさせる。そして、怒るときは陰で怒る。よくCS(カスタマーサティスファクション)が大切と言われるが、CSの前にES(エンプロイーサティスファクション)がなければならない。良い環境で社員に心身ともに満足して働いてもらうことではじめて、お客さまへのサービスが十分に果たせると考えている。つまり、ESあってのCSだということだ」
──社員に何を求める。
「人間は生きているうちに尊敬できる人、すごいと思える人に何人会えるかが醍醐味だ。人との出会いに気づくか気づかないかで人生は変わってくる。人間はじっとしていても始まらない。私は社員に『とにかく行動しなさい、人や現象に出会いなさい、出会いに気づきなさい、気づいたらそれを受け入れなさい、受け入れたらそれを発信しなさい』と言っている。そうすると自分を含めて周りが変わっていく。これを『セレンディピティ』(偶然の出会いを自分の幸運につなげる能力)という言葉で表現している」
──セレンディピティを高めるためには。
「人や現象への気づきは感性によって得られるが、教養も重要だ。情報の引き出しが多い方がいい」
「出会いに気づいたら、まずそれを受け入れて、発信することだ。発信した人の思いが伝わって、話が弾み、『この人は面白い人だ』ともう1回会ってくれる。そして、いいアイデアに気付いたら、やはり、発信する。それがいいものであれば、『君、面白いことを言うじゃないか』『やろう』となってくる。帝国ホテルの120余年の歴史の中で現場の発想から出てきたサービスはたくさんある」
──そのほか社員に伝えていることは。
「社会人としては『誠実、謙虚、感謝』の三つが重要で、帝国ホテルで働く者としては、『素直で、明るく、元気よく』を含めた六つが求められる。この六つの素質を備えている人は間違ったことはしないと考えている。お客さまの心をつかむおもてなしの原点はそこにあるはずだ」
【こばやし・てつや】