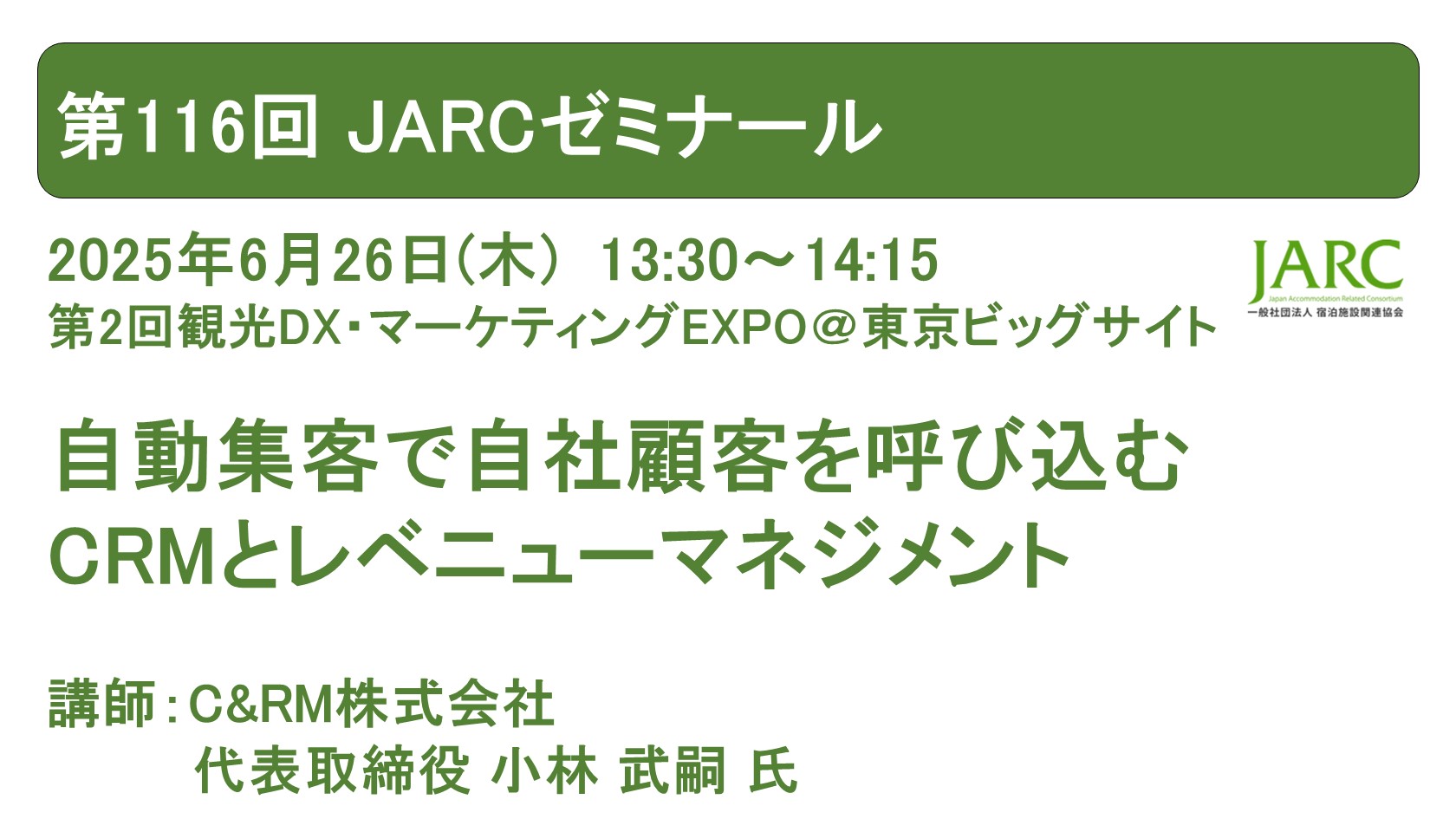徳江准教授
明治以後、わが国の元号は一世一元の制となり、元号は天皇在位中に変更されることがなくなったが、以前はそうでなかったことは周知の事実であろう。大規模な天災や疫病の蔓延などがあった際、かつては元号が改元されていた。在位中に何度か改元されたケースも多い。そういった意味では、令和になってからは未曾有の台風・大雨被害、新型コロナウィルスの蔓延など、昔であれば間違いなく改元されていたような状況となっている。
こうした環境下で、残念ながら、ホテル・旅館、ブライダル、料飲サービスといったホスピタリティ産業では、大幅な売り上げの落ち込みとともに、事業継続を断念するケースが出現してしまっている。筆者もかつて飲食店を経営していたことがあり、米国同時多発テロでも、リーマンショックでも、SARS騒ぎでも非常に苦しかったが、特定地域や特定業界の話であったため、なんとか事業継続がかなった。しかし、今も経営していたとすれば、私は間違いなく諦めていただろう。
こうした状況に対して、「だから観光立国なんて目指さなければよかったんだ」とか、「インバウンドなんか狙っているからだ」といった否定的な見解が散見されるようになってきた。ただ、こうした主張をする人は、「ではどうすべきか?」といった建設的な意見を述べることがあまりないように感じられる。わが国の経済規模を踏まえれば、「観光立国」とはいえモルディブのように観光のウェイトを高めるには限界がある。しかし、他国企業と厳しい競争を展開する他の産業の競争力を維持するためにも、成長余地が残っている観光を重点的に扱うというのがわが国の「観光立国」ではなかったか。
2020年5月上旬時点では、欧米諸国の膨大な死者数に比べれば、わが国の犠牲は相対的に少なく推移している。直前まで満員電車で毎日の通勤が行なわれていたにもかかわらず、である。被害が比較的抑えられている理由はさまざまに検討されているが、接触の少ない国民性、靴を脱ぐあるいは手洗いといった生活習慣、入浴などが挙げられている。これは、実は「ポスト・コロナ」あるいは「ウィズ・コロナ」の時代においては、わが国ホスピタリティ産業にとってむしろ強みにさえなるのではないだろうか。世界中の人々に対して、「清潔な国・日本」が、やはりデスティネーションとしての魅力を訴求できる可能性も垣間見えるからである。
ただし、修正すべき点も浮き彫りになった。これまでは、「濃厚」な「接触」によるサービス提供が良しとされてきたが、IT技術の革新を通じて、不要な接触は減らせる可能性が共有されつつある。きっと、新しい時代の新しいホスピタリティが必要とされるようになるだろう。大学でも、リモート講義を強いられたがために、逆にその良さに気づいた教員も多くいる。今回の悲劇を機会ととらえ前向きな対応を目指すことが、今のホスピタリティ産業になにより求められているように感じられる。

徳江准教授