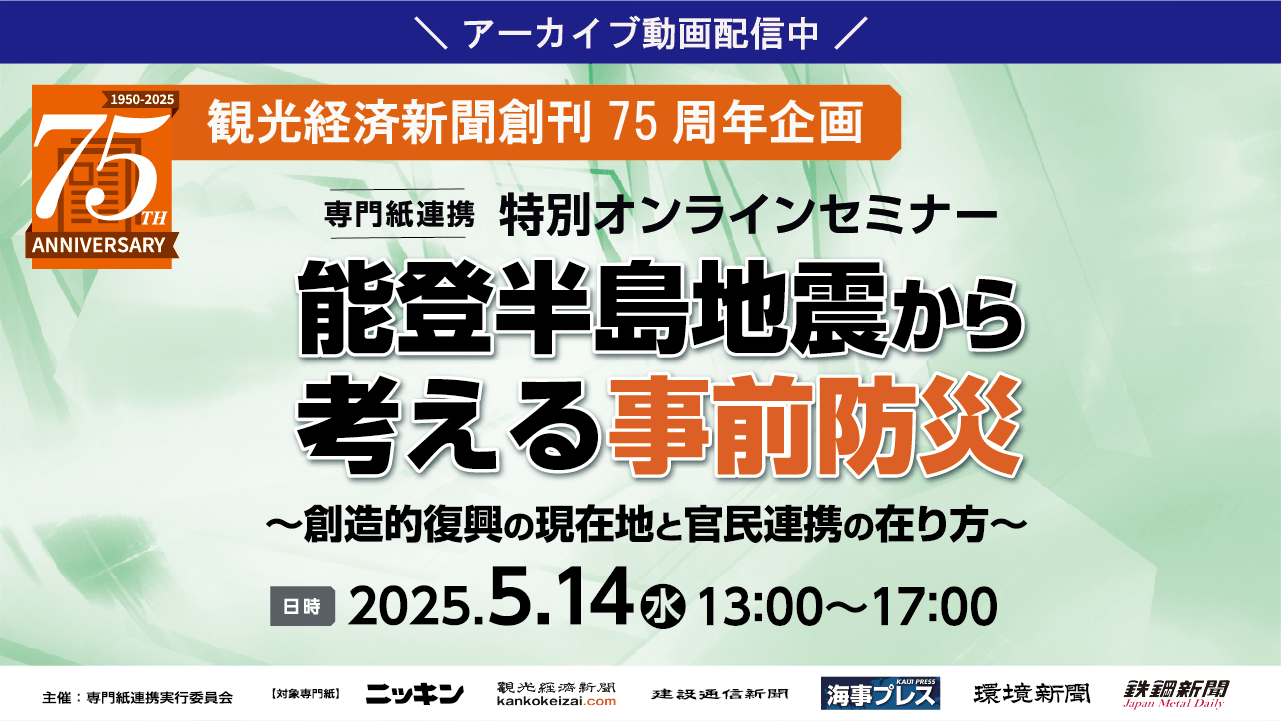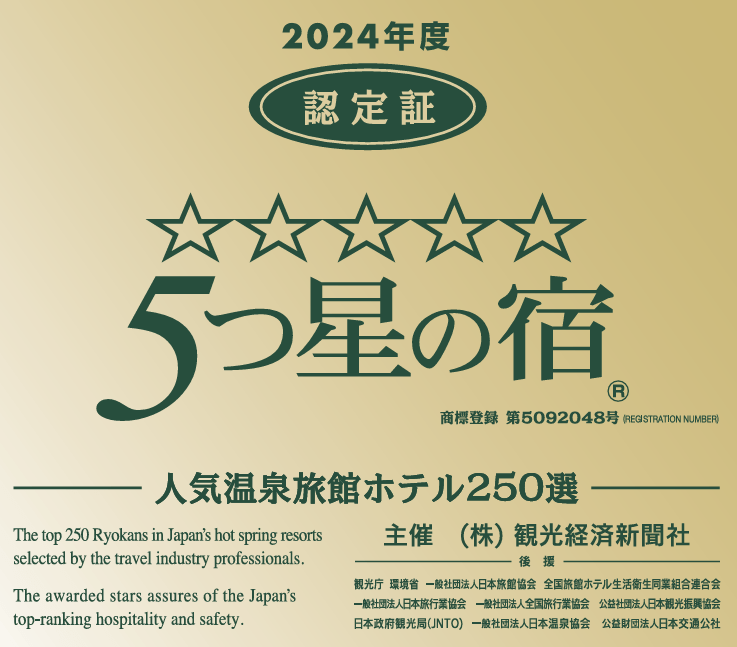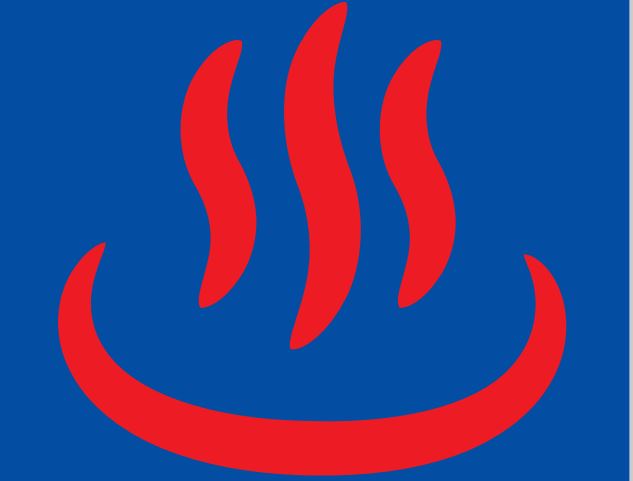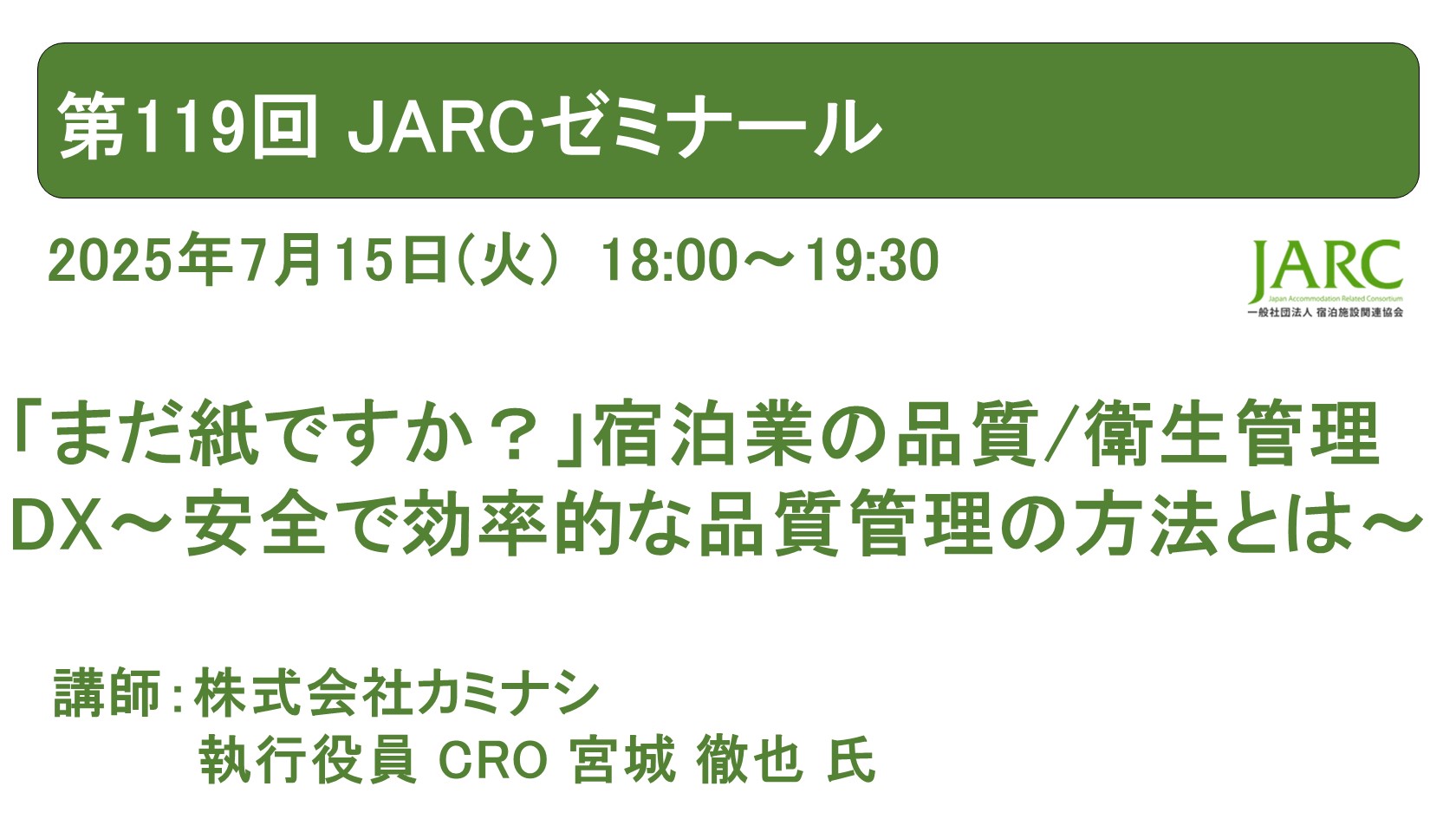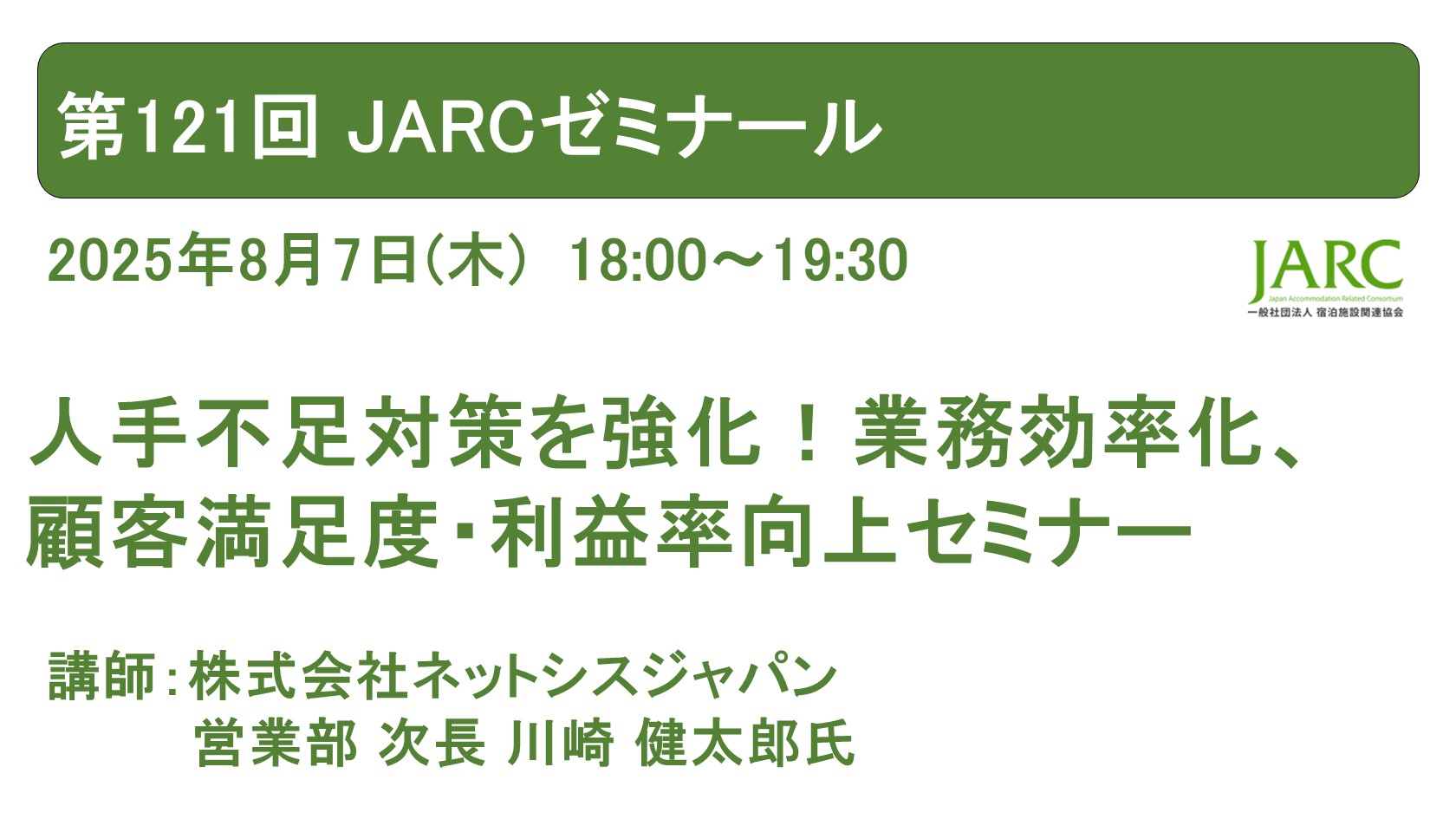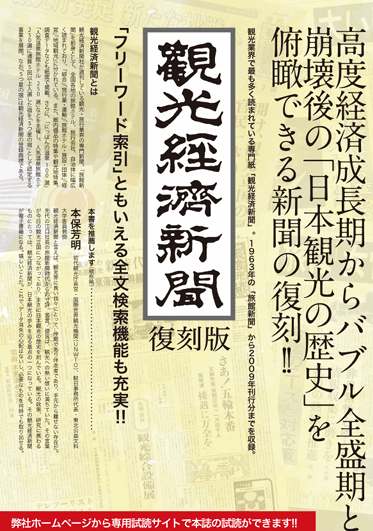伏見とうがらし
前号に続き、「旅館こうろ」でいただいたみやびやかな京料理について、第2弾。
八寸の1品として供された「鳥貝握り」。実はコレ、タダの鳥貝ではないのだ。公益社団法人京のふるさと産品協会が認定する、たった31品目しかない「京のブランド産品」に選ばれた、「丹後とり貝」である。
元々京都北端丹後地域の、日本海に面する舞鶴湾や若狭湾は、鳥貝の名産地。だが、貧酸素に弱く大量に死ぬことがあるため、漁の豊凶が安定しなかった。そこで京都府立海洋センターが稚貝の育成を研究し、見事成功。1年かけてじっくり育てるため、一般の物より重さが2~3倍と大きく、全重量100グラム以上のものが「丹後とり貝」と認定されているそうだ。
鮮度保持が難しく、殻をむき、湯引きした冷凍品が最も多く出回っている。だが、この「丹後とり貝」は活(い)けでも流通しており、当日握り寿司(ずし)のネタとして登場したのも、活けをサッと湯がいたもの。肉厚で軟らか、驚くほど深い甘味がある。
同じく「京のブランド産品」に、魚類で唯一選出されたのが「丹後ぐじ」。若狭湾に面した京都府宮津市や伊根町で水揚げされるアカアマダイで、さまざまな基準をクリアしたものだけが「丹後ぐじ」と呼ばれる。
身が軟らかく傷みやすいため徹底的な鮮度管理が必要で、釣り上げると人間の体温の影響を受けないよう一切触らずに、針を外さず釣り糸を切るという。そして魚体に直接氷が触れない構造で、水温を4度に維持したクーラーボックスに入れ、鮮度と奇麗なピンク色を保つらしい。
その新鮮な「丹後ぐじ」、なんとお造りで登場した。甘ダイを生で食したのは初めてだ。細造りにした身を加減酢でいただいたが、繊細な甘味と旨味にはしょうゆより相性が良く、超美味。
別皿で同時に運ばれたのは、皮の素揚げ。甘ダイと言えば、熱した油を皮目にかけ、うろこを逆立てた松笠焼きがポピュラーだが、刺し身にして残った皮も、揚げてすだちを添えれば立派な1品になる。パリッパリの皮のウマイこと! 薄桃色の身とは見た目も食感も対照的で、とても楽しめた。
前号でご紹介した村沢牛、今度はサーロインの陶板焼きで再登板。添えられていたのは「伏見とうがらし」で、これも「京のブランド産品」かつ京都市内で栽培されている「京の伝統野菜」だ。江戸時代の書物にこの唐辛子について記述があり、古くから栽培されていたと分かる。通常10~15センチ、長いもので20センチにもなり、唐辛子の中では最も細長い品種で「ひもとう」とも呼ばれるそうだ。
この甘い唐辛子、赤く熟した「赤伏見」も添えられていた。珍しいから高価だそう。焼いて焦げ目を付けてあり、目に鮮やかなだけでなく、食してなお美味。
北原茂樹会長のこだわりには脱帽である。他にも、まだまだご紹介すべき京野菜がたくさんある。祇園祭にまつわる食文化にも触れたい。…というワケで、次号はもう一度京都の食について。お楽しみに!
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。

丹後くじと皮の素揚げ

伏見とうがらし