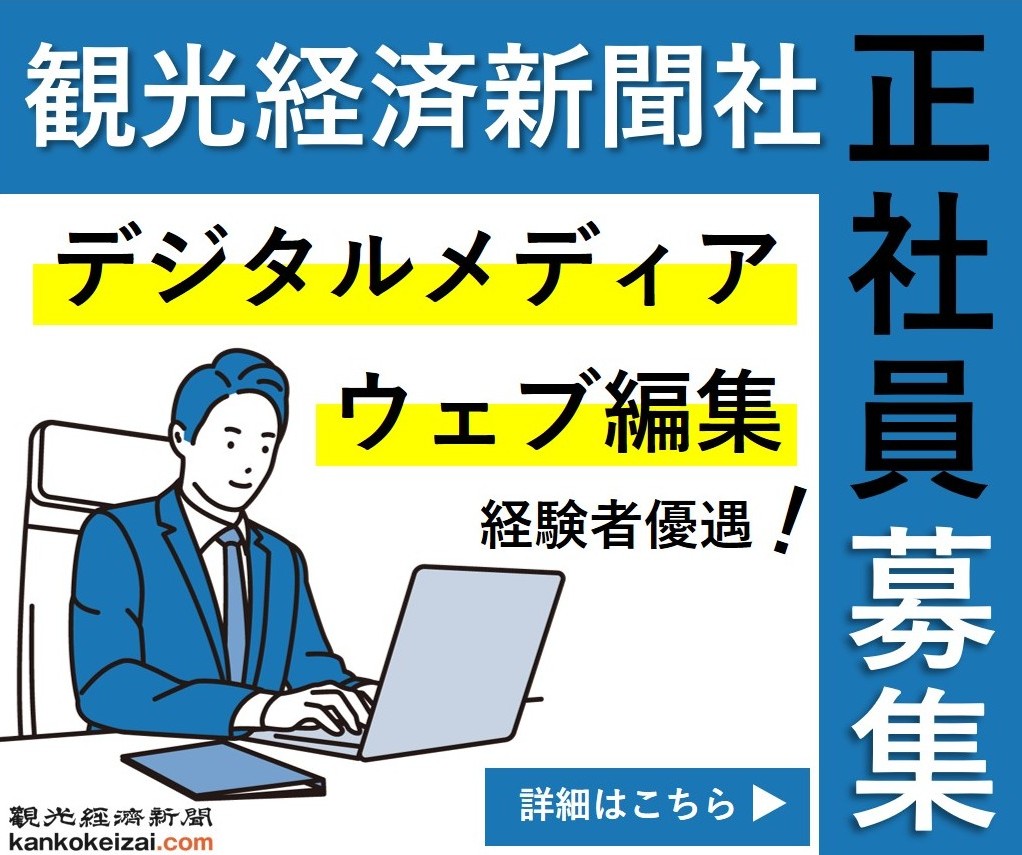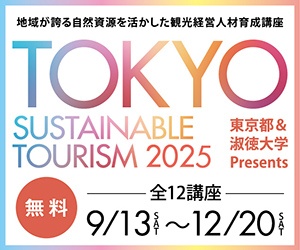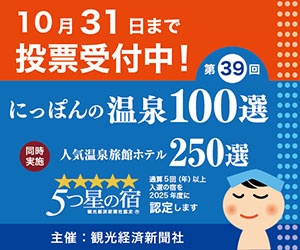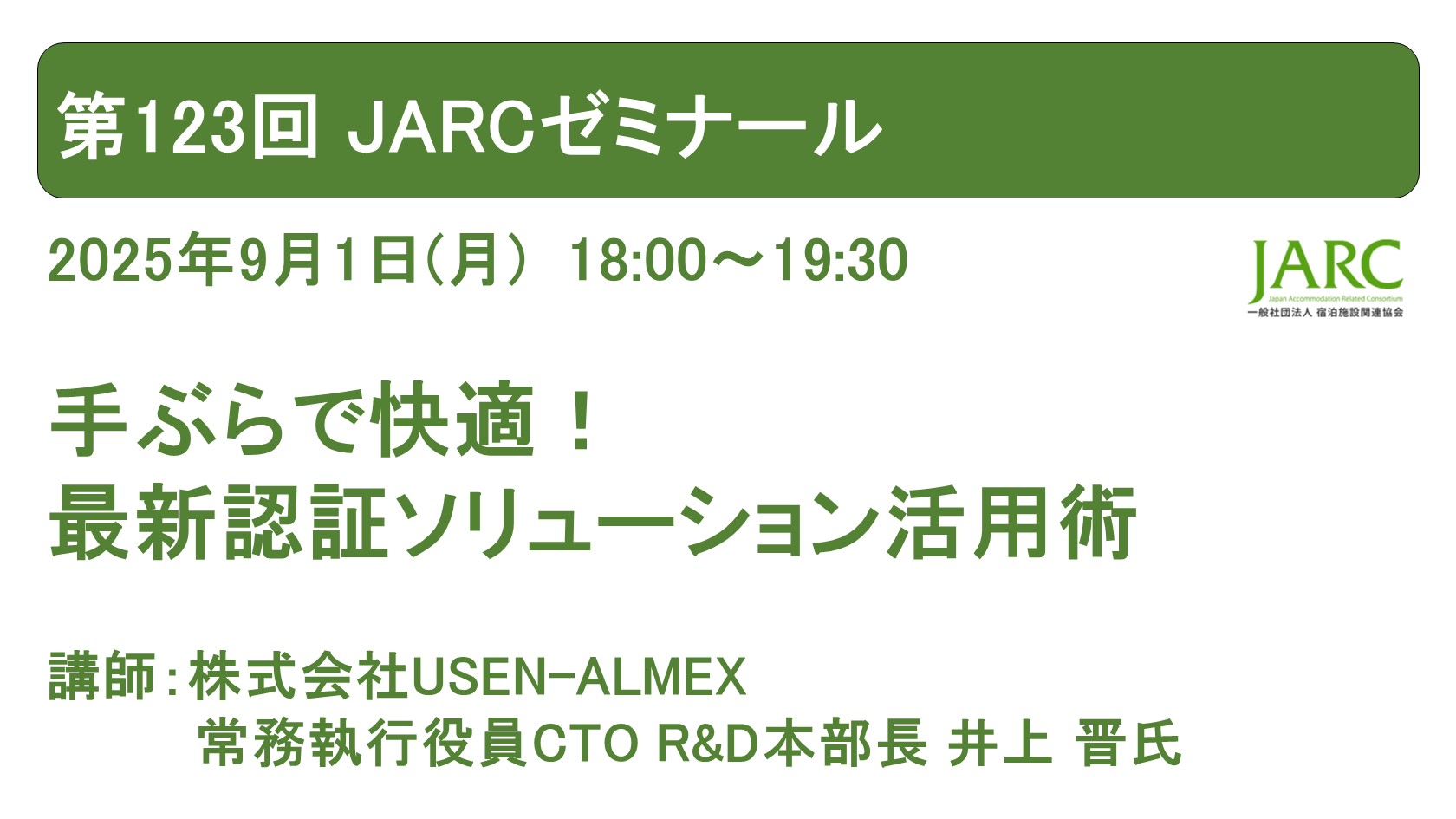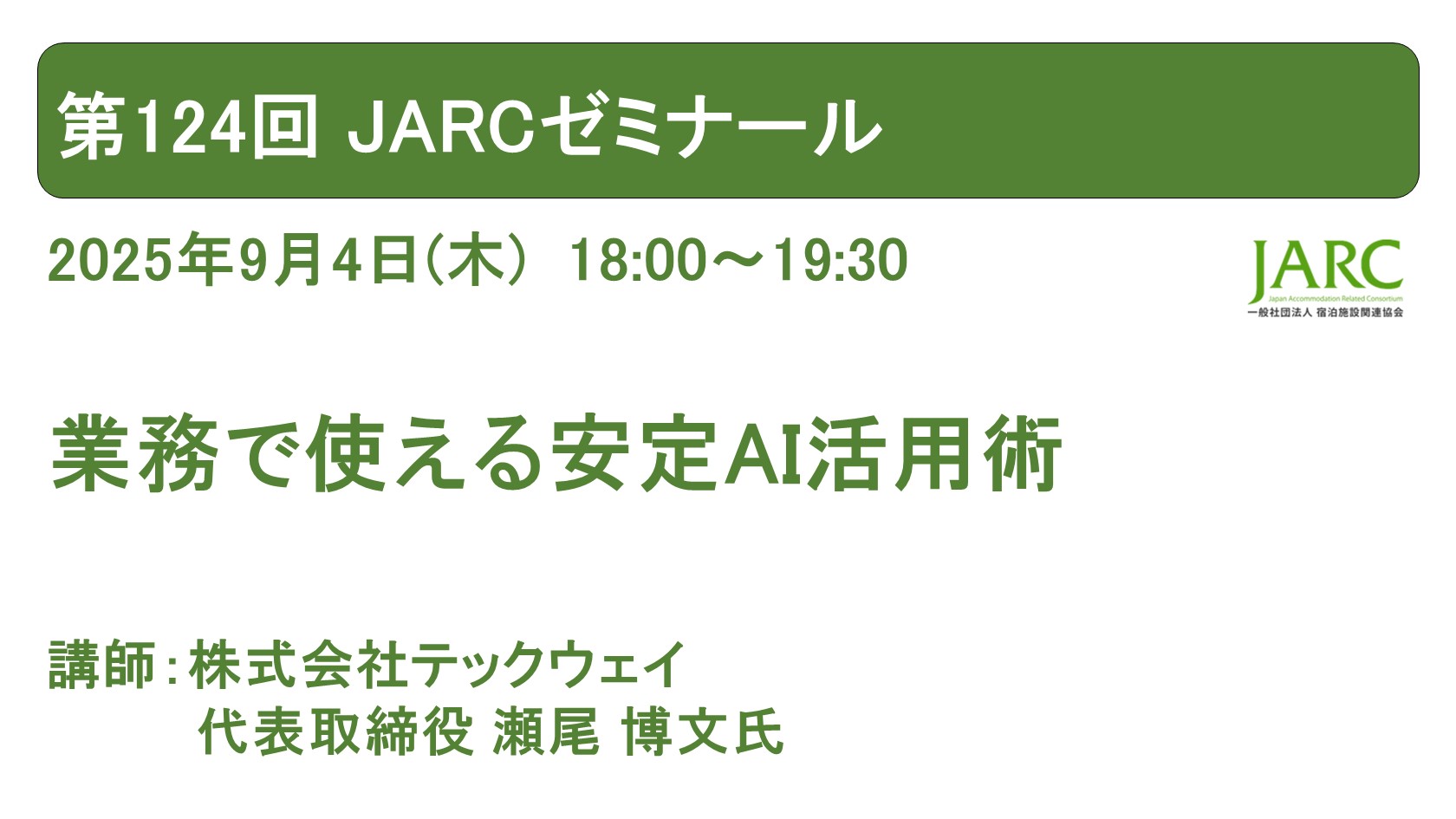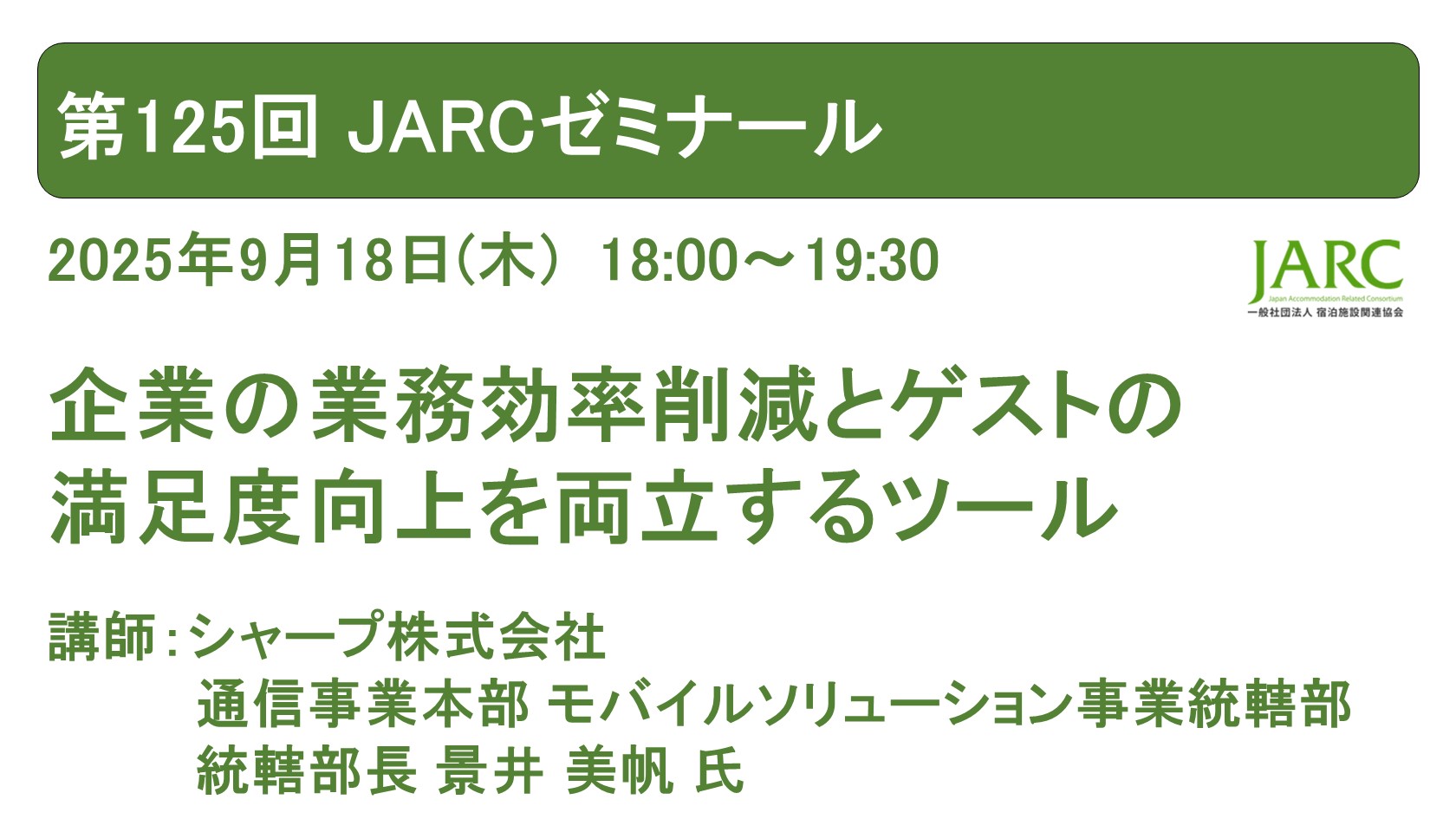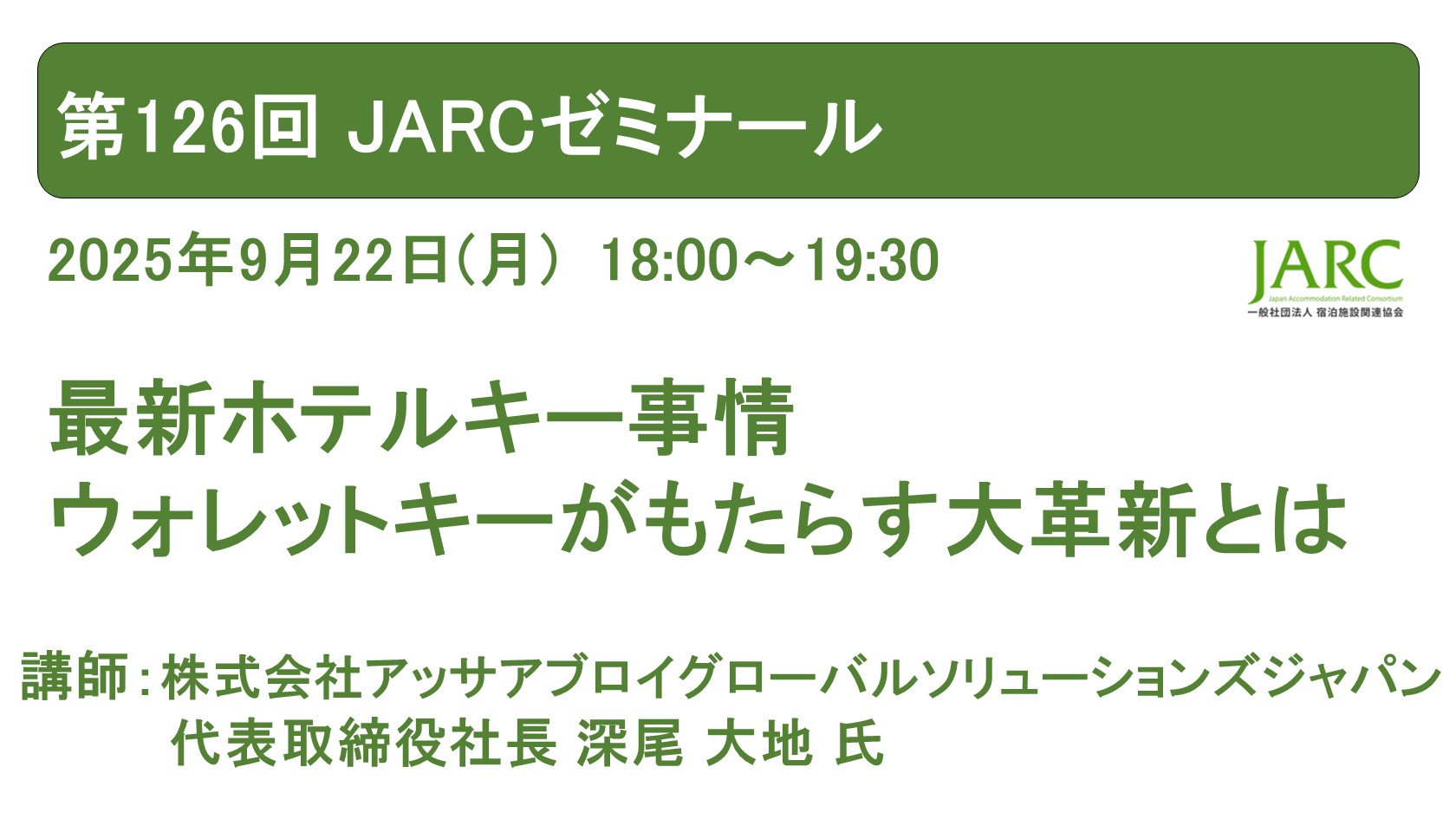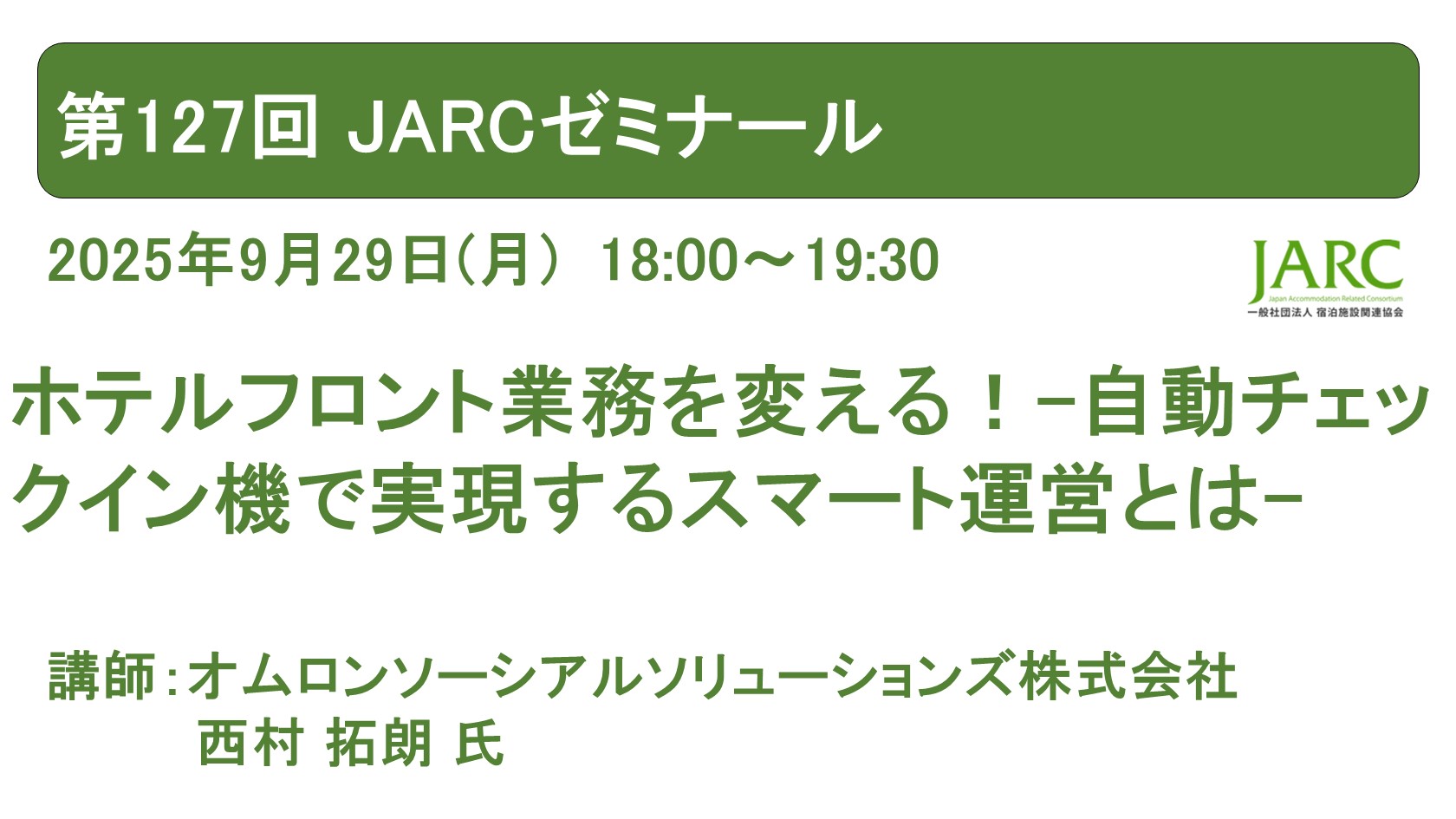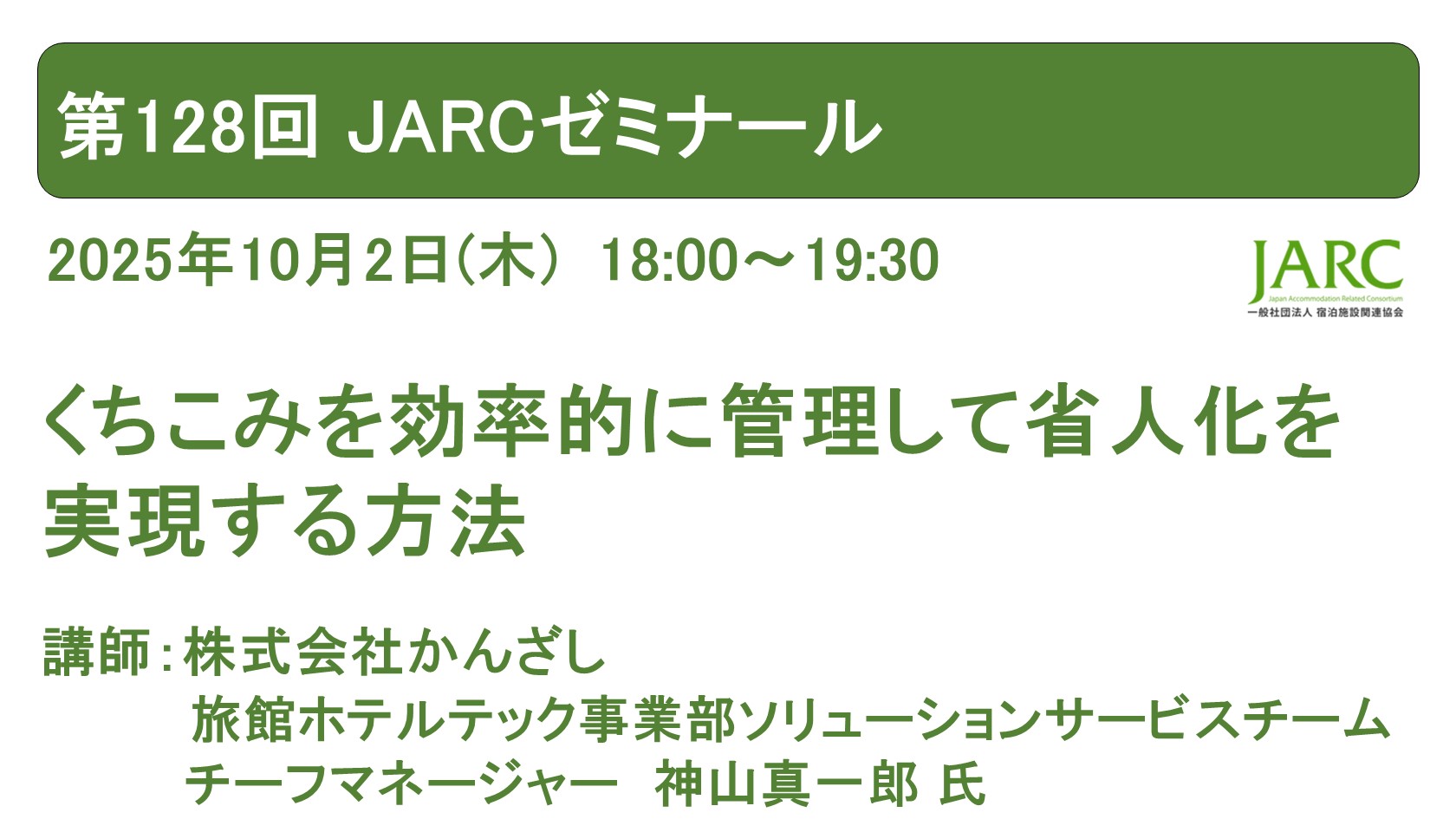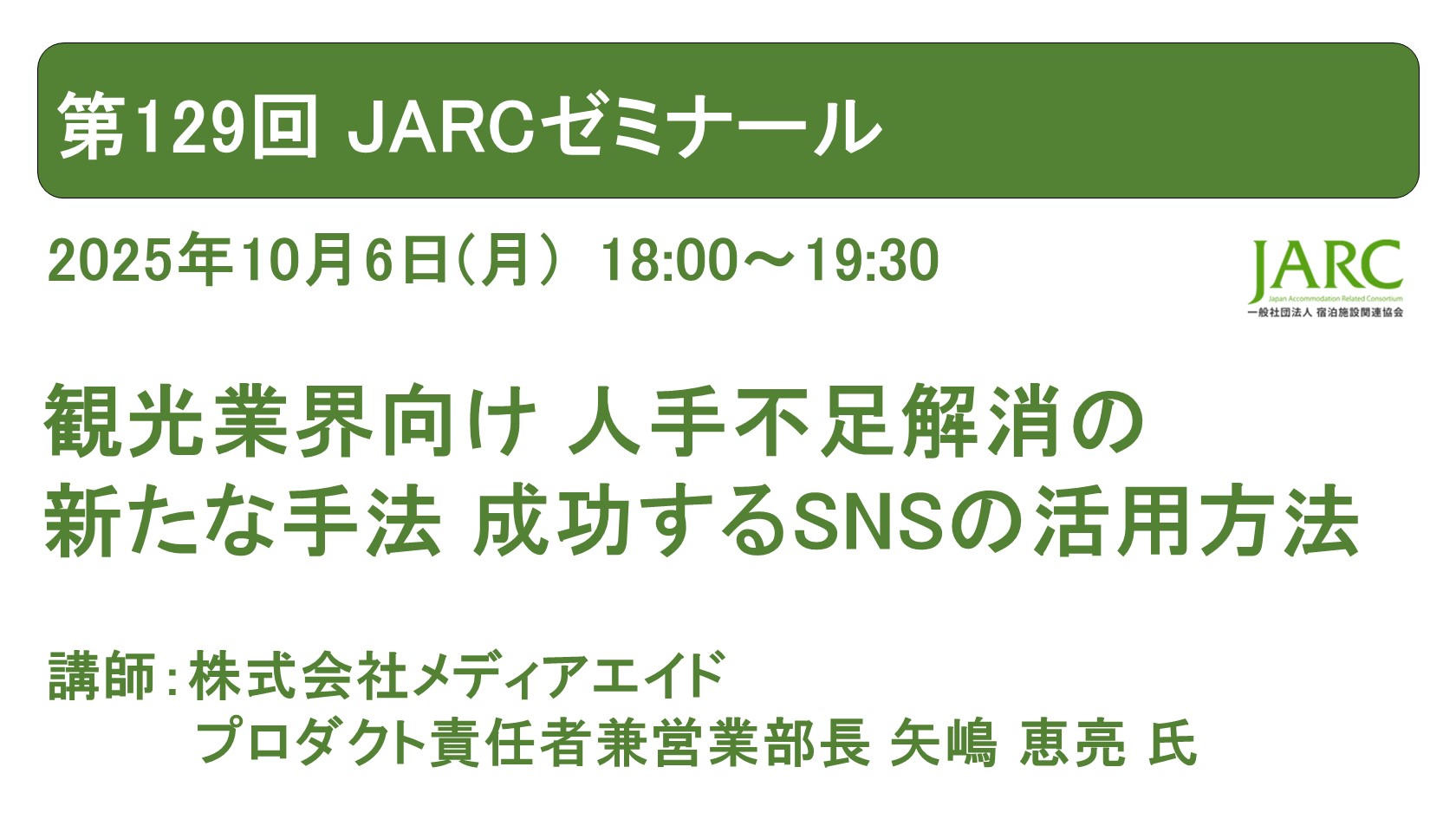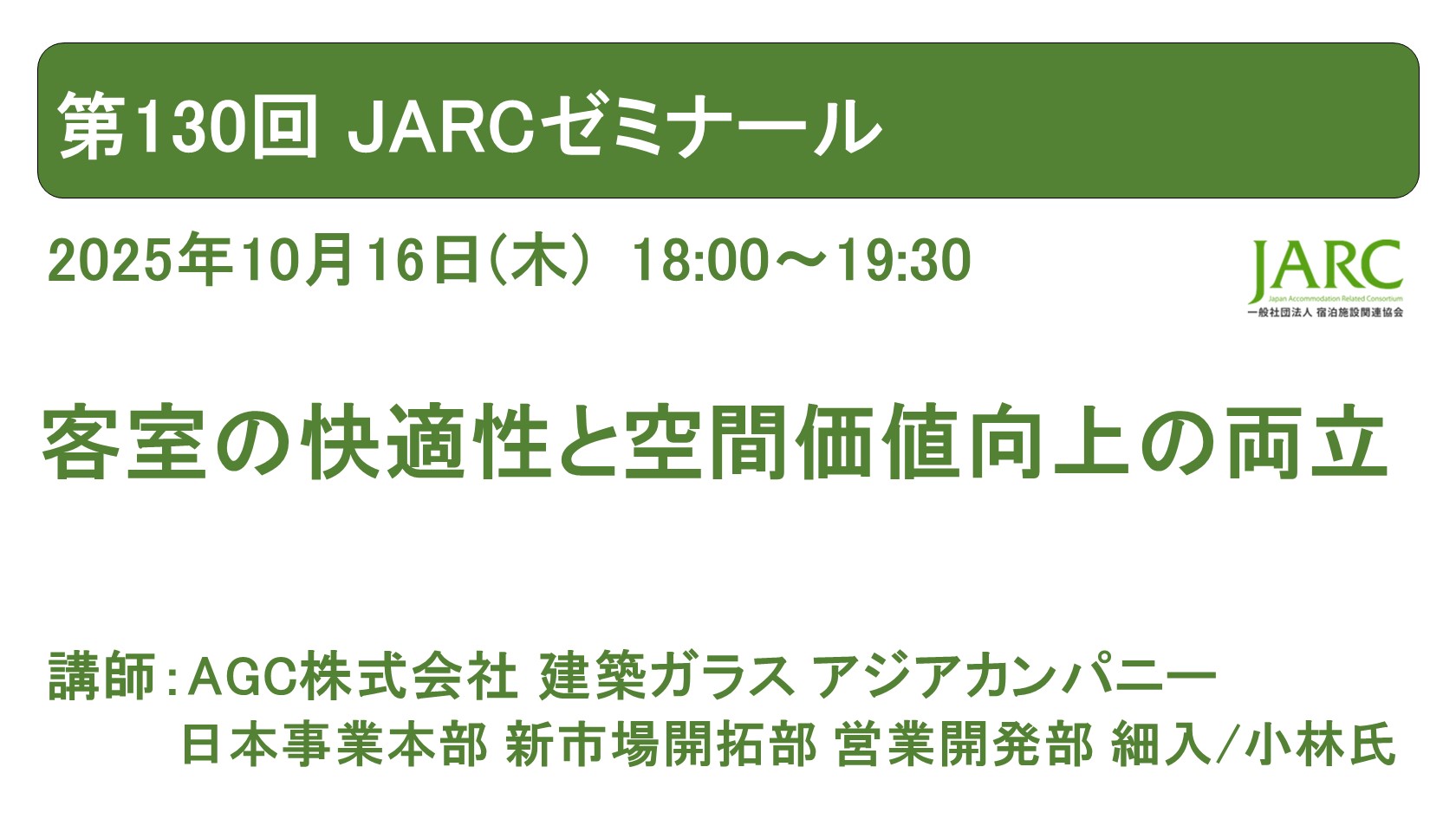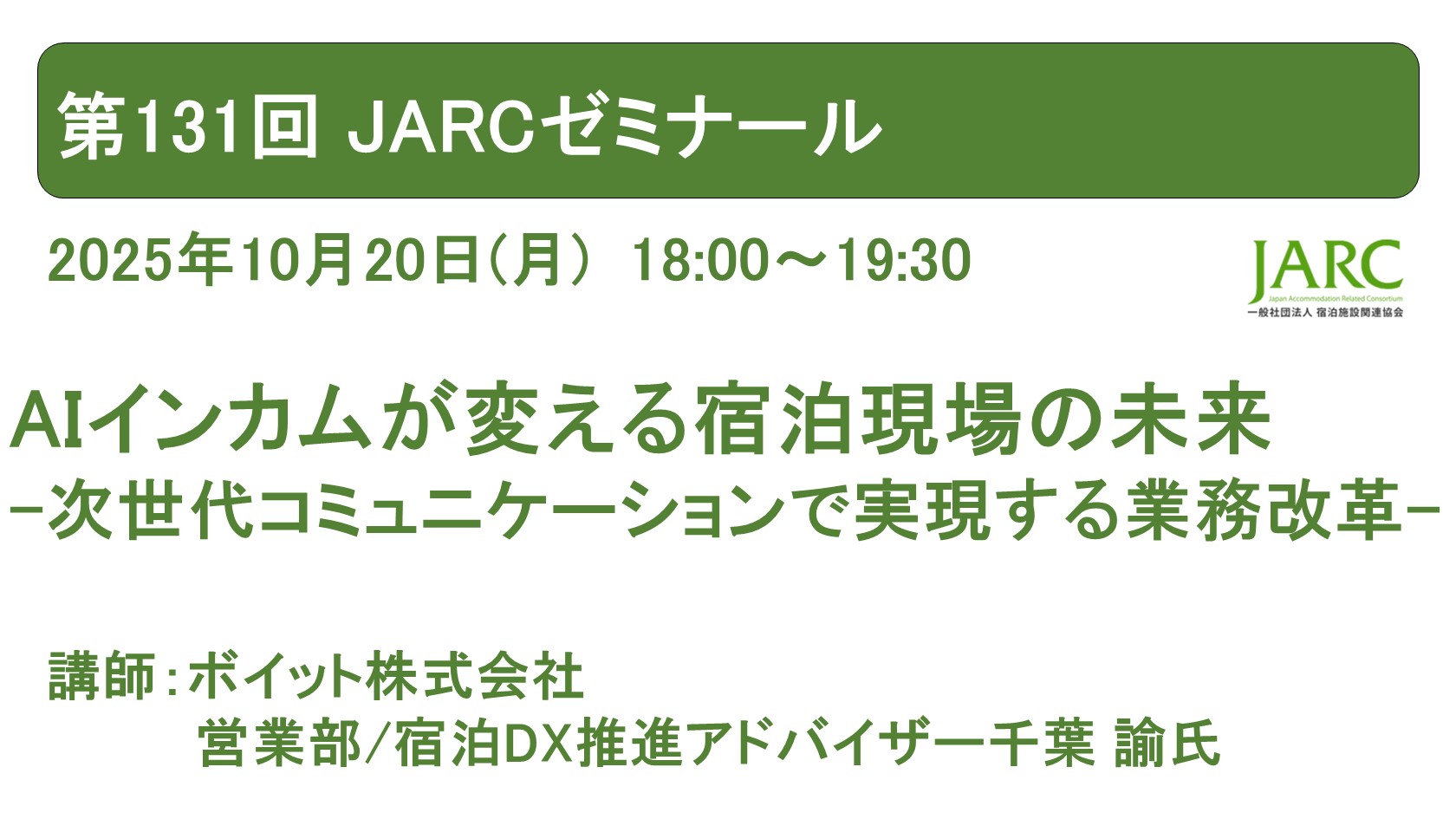私はもうすぐ79歳になる老人であるが、現在の日本の極めて情けない体たらくについては、死んでも死に切れない残念無念な想いを感じ続けている。現在の日本は経済格差の拡大や社会的閉塞(へいそく)感が人々の心を深刻にむしばんでいる。人間が人間として生きていく上で必要な尊厳が軽んじられている現実は看過できない。老骨にむちを打ちながら閉塞感に満ちた現状を打破しないといけないと感じる日々の中、現状の日本でパーマカルチャー(Permaculture)に対する関心が高まりつつあることに着目した。
パーマカルチャーとは、パーマネント(永続性)、アグリカルチャー(農業)、カルチャー(文化)を組み合わせた造語である。永続可能な循環型の農業をもとに、自然と人間が共に豊かになるような関係性を築いていくためのデザイン手法が意味されている。無農薬、有機農業を基本にしながら、自然の循環を生かした持続可能な暮らしの実現を目指す動きである。
パーマカルチャーは、オーストラリアのB・モリソンとD・ホルムグレンが1974年に提唱したのが始まりで、その後に世界各地に広がっていった。モリソンは1928年にタスマニアで生まれ、猟師や漁師などを経て、連邦調査機関で野生生物の研究員に採用され、その後にタスマニア大学の教員を務めた。その間に自然環境が壊され、野生生物が急速に失われていく現実を危惧して、パーマカルチャーの必要性を実感した。一方、ホルムグレンは1955年生まれで、環境デザインを学ぶ中でモリソンの考えに共鳴して、パーマカルチャーに関わる倫理やデザイン原則を提案した。
 会員向け記事です。
会員向け記事です。