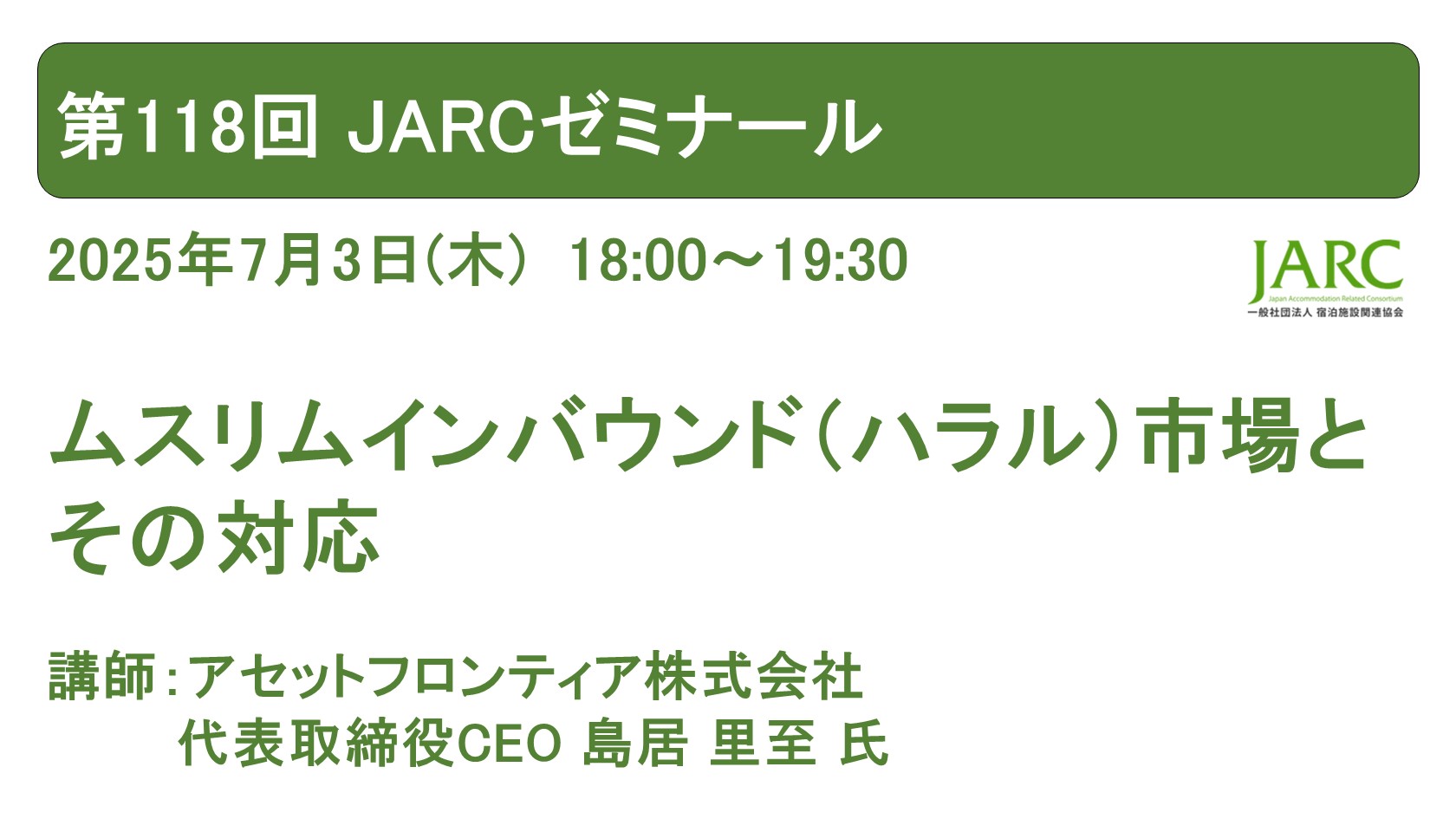浅草の中心部では、時の観光トレンドを反映して、タピオカ、パンケーキ、和栗モンブラン、イチゴといったものを扱う店が増えては入れ替わるという現象が続いている。一時的なブームもあれば、定着しているものもあり、集客力のある浅草といえど経営の難しさというものを実感する。そんな中、最近急増中の形態として二つのキーワードが上げられる。もんじゃと神戸牛だ。今回はもんじゃをひもといてみたい。
浅草は月島と並んで二大もんじゃ聖地とされている。今では月島の方がもんじゃのイメージが浸透した感もあるが、歴史をさかのぼると、浅草の方が江戸時代からの手法をそのまま引き継いでいるといわれている。もんじゃというと具材を先に入れ、鉄板で具材を炒めてドーナツ型の土手を作り、そこに生地になるだしを入れるというスタイルが広まっている。これは月島流で、昭和20年代に登場したモデルが各所に広まったスタイルだ。昭和30年代にはわずか4軒だったが、令和元年6月時点では月島もんじゃ振興会に加入している店は34社54店舗にまで増えたとされる。なお、月島の半径500メートルくらいの通称もんじゃストリートかいわいには、振興会に加入していない店も含めると80店舗以上はあるといわれている。ある意味、もんじゃの一大聖地といってもいいだろう。
 会員向け記事です。
会員向け記事です。