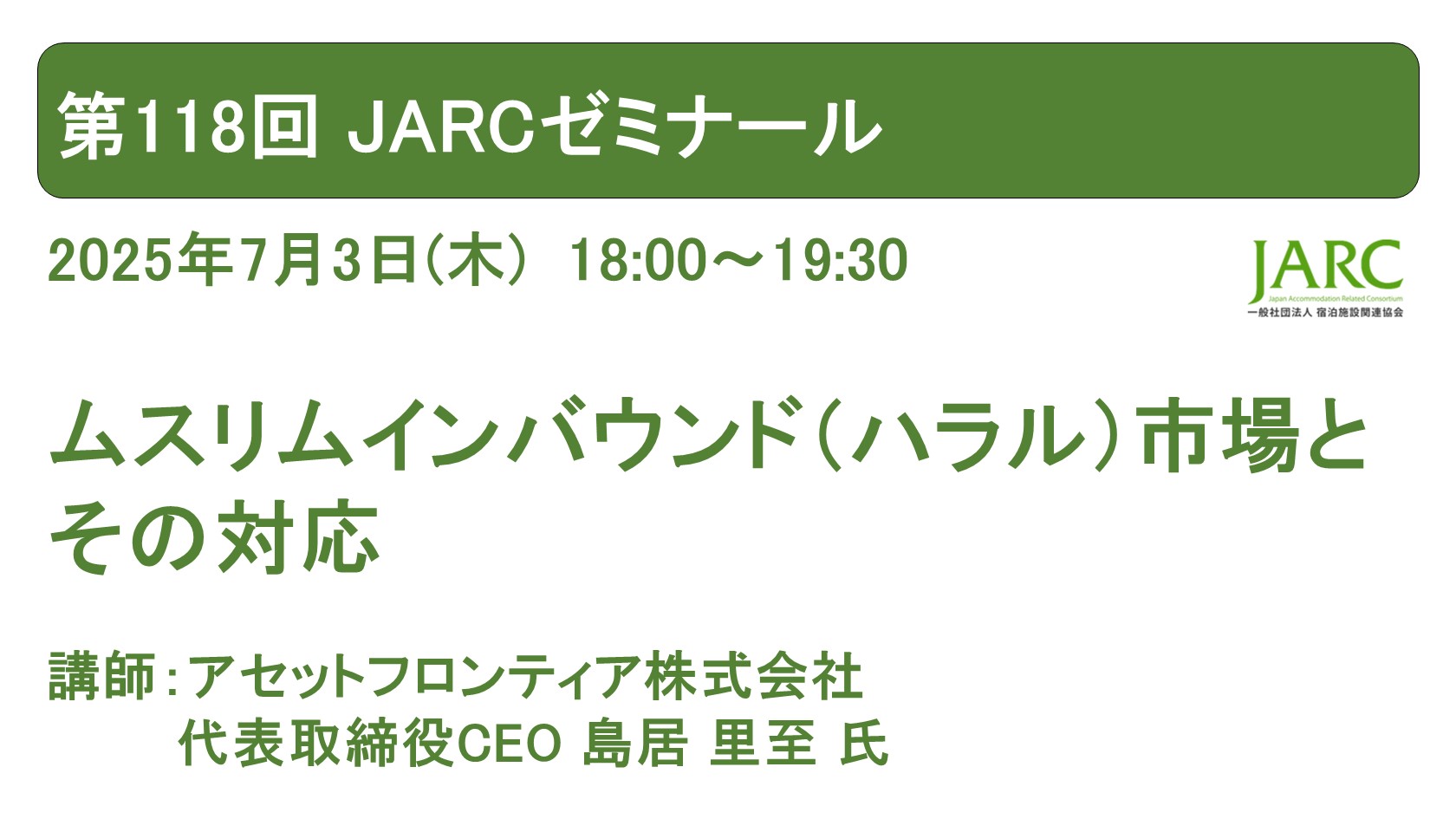最近の政府の政策決定と実施のスピードには驚く。知らぬ間に年金制度が変わり、マイナンバーが徹底され、今度はプレミアム・フライデーだ。これまでの意思決定があまりにも遅いもので景気回復につながらず、時代に置いていかれるという危惧があるからだろうか。
その焦燥感は分からないでもない。GDPは中国に抜かれて久しく、桁外れの第3位、1人当たり生産性に至っては世界26位だ。サービス業の中でも宿泊・料飲部門が欧米の4割以下と極めて低い。ものづくり大国・日本は過去のもの、雇用者の7割がサービス業で、これが比較的高い製造業の足を引っ張っている。
労働集約型のこの産業は海外移転やロボット化が難しく、結果、価格競争やサービス合戦といった国内抗争に走りがちだ。おまけに人手不足が重なり、恒常的な残業体質となる。
電通社員の過労自殺にはじまった残業問題は大手旅行業者の労基法違反・書類送検へと広がり、燎原の火はアスクルの倉庫火災やクロネコヤマトの業務縮小といった物流の問題へと拡散している。
そこでいよいよ政府の手によって前代未聞の「働き方革命」のノロシが挙がった。月末の金曜日は3時に仕事を切り上げよう、というものだ。経済効果を期待する向きもある一方で、持ち帰り残業を増やすだけだという冷ややかな反応もある。実際に実施した企業は2%程度に過ぎなかったという調査も。焼け石に水でも掛けないよりはましではあろうが、われらの低生産性はどうしたらいいのだろう。世界順位など、為替変動や中身の吟味がないのだから一喜一憂する必要がないという意見もある。
確かに提供されるサービスの質の違いは数値化できない。日本の「おもてなし」水準は群を抜いて高いので手間暇もかかる。おまけにお客の要求水準も高い。言い換えれば消費者は割安で高度なサービスを受けていることになる。日本人には当たり前のことが訪日外客には感動を与える。
大切なのは国際順位ではない。絶対生産性の着実な向上だ。品質÷価格が生産性を決めるので、大手なら大量仕入れや人件費抑制によって価格を下げることが可能だろう。しかし人手不足の中小には土台無理な話で、品質を高める、つまり独自の付加価値をつけるしか手はない。それはモデル化できるものではなく、事業者のセンスとアイデア次第だ。ハードよりはソフト、地域ならではのストーリーや独自の「人」を押し出したブランド化が欠かせない。生産性向上の秘訣は、知恵を絞ってそれをやるかやらないかにかかっている。
(亜細亜大学教授)