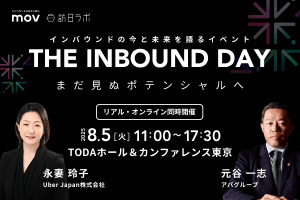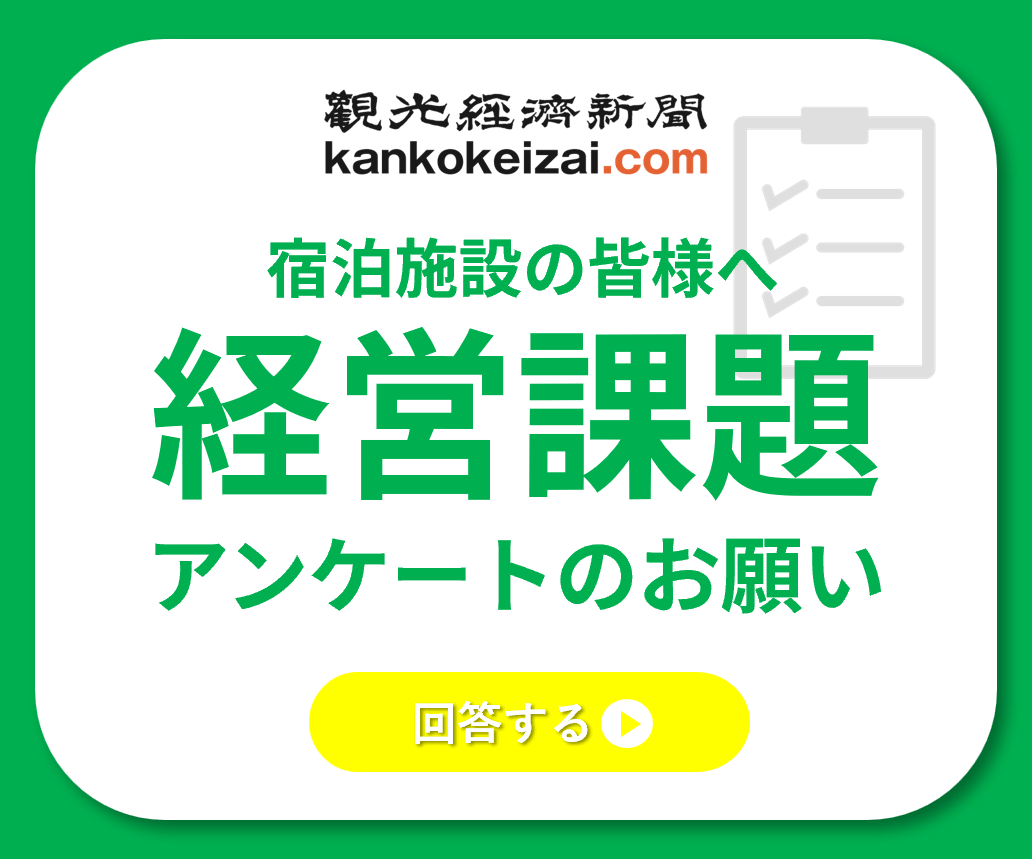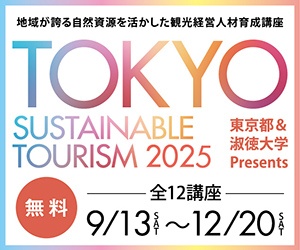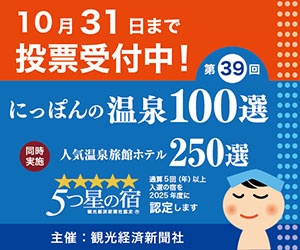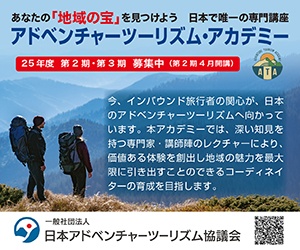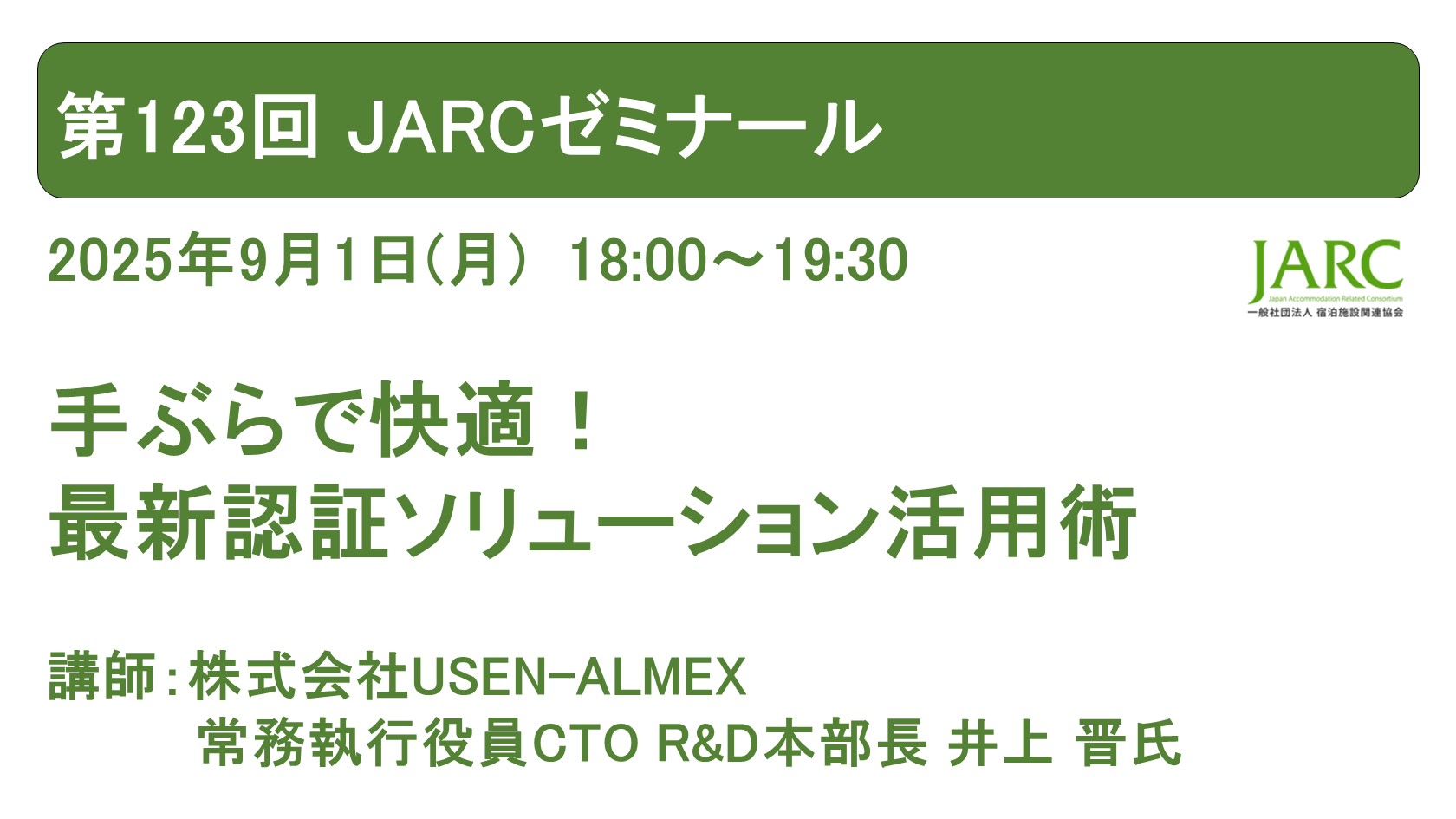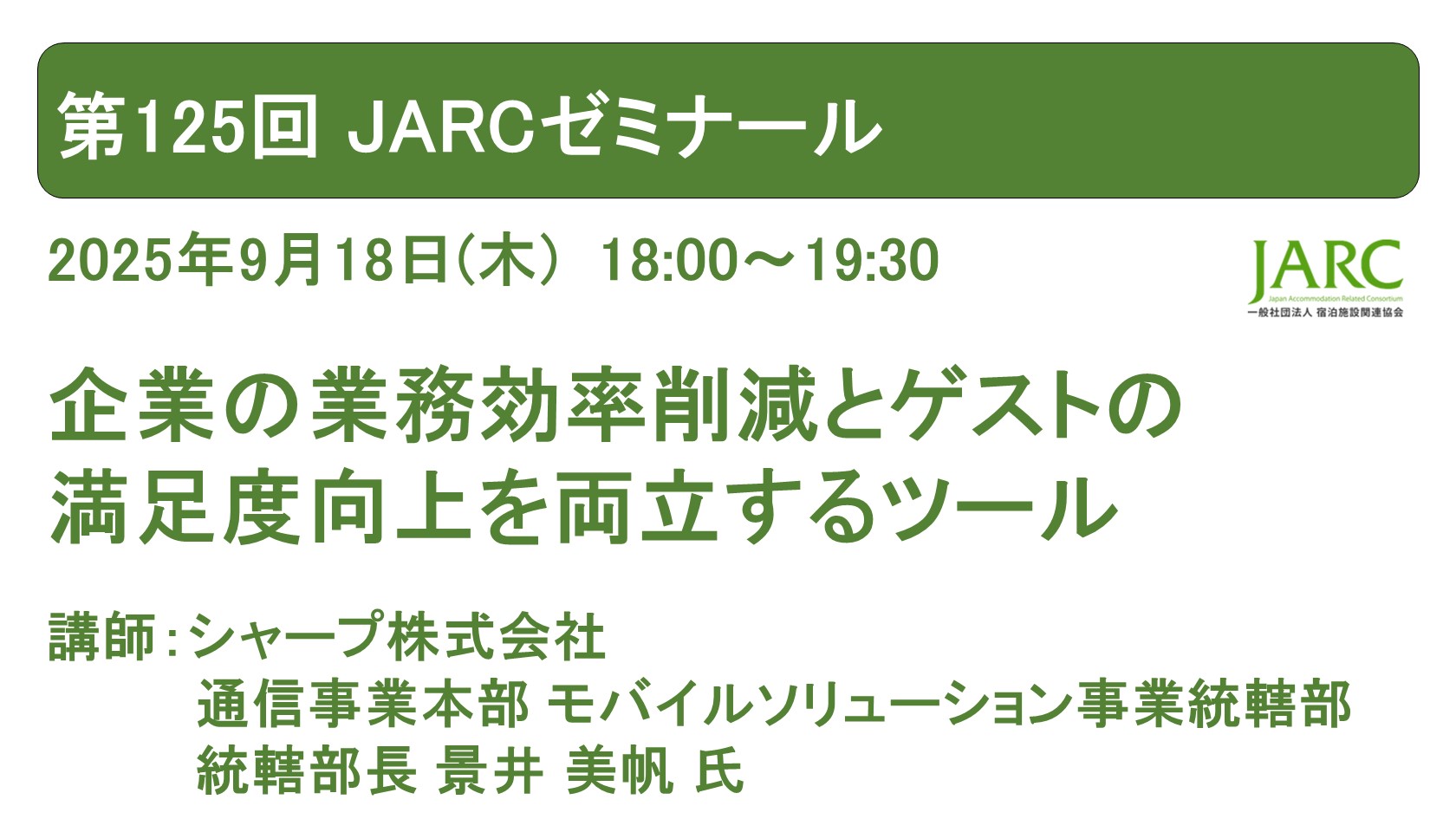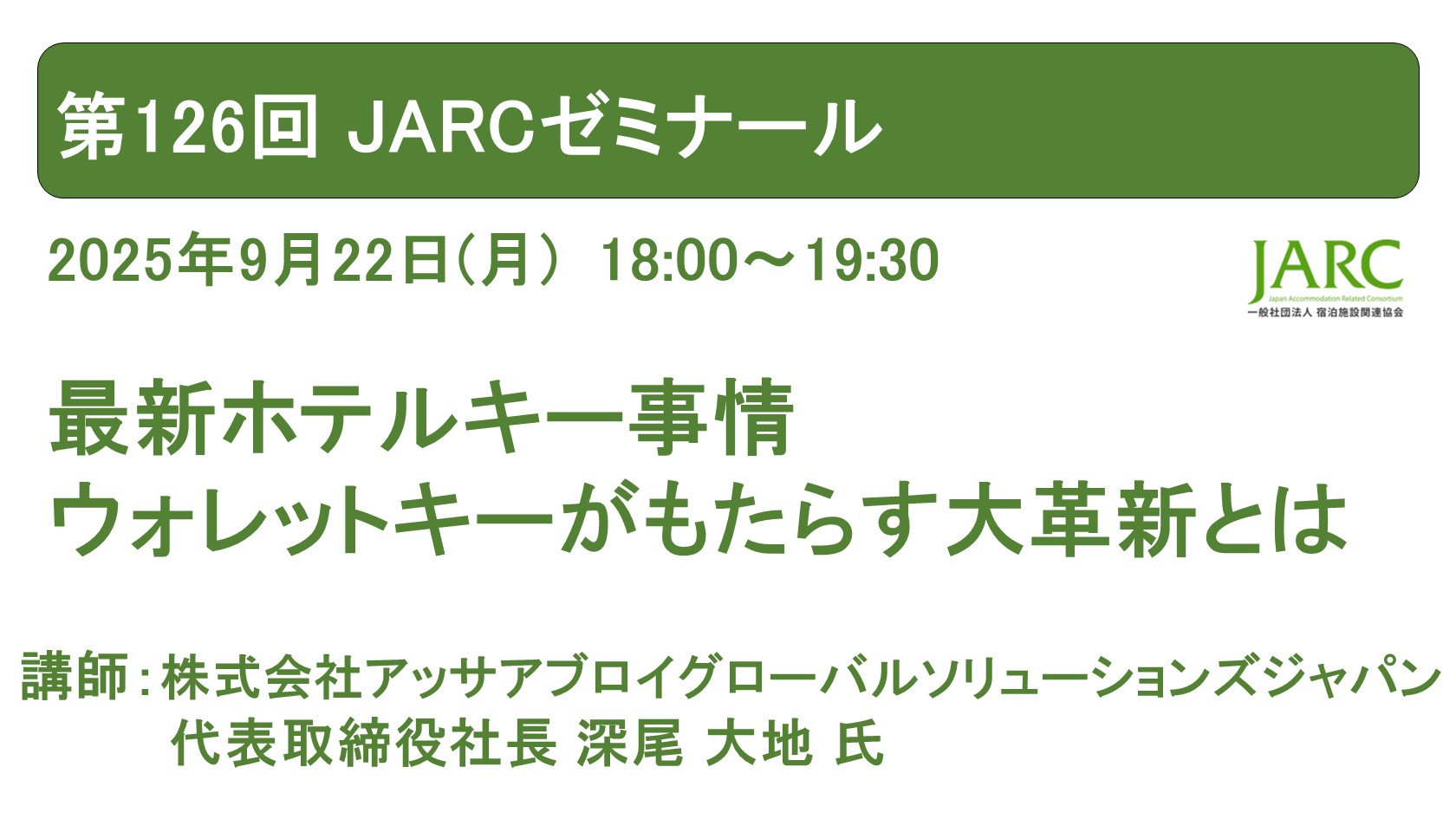7月1日、福島県金山町で「只見線の新しい歴史を創る」シンポジウムが開催された。2011年夏の集中豪雨により一部区間運休が続いている只見線に関しては、これまでもシンポジウムが何回も開催されてきたが、今回ほど熱気に包まれた集会はなかった。
というのも、不通になっている会津川口・只見間について6月19日にJR東日本と福島県との間で、JR初となる「上下分離」による鉄道の復旧が正式に決定したばかりだからだ。早ければ来年度着工して、21年には運行再開になるという。
この決定により、鉄道による全面復旧を要望してきた福島県や奥会津の地元は、6年目にしてようやく復興の仕上げに入ることができた。が、同時にいばらの道も覚悟することになった。復旧工事費は81億円と想定され、3分の2は地元負担になるからだ。
それだけではなく、只見線全体の1日1キロ当たり平均輸送人員は370人(10年度)、不通区間ではわずか49人しかいないために、復旧後でも鉄道施設や土地を保有する福島県など地元自治体には相当の財政負担が生じると予想されるからだ。
それでも、福島県知事や地元自治体、住民の鉄道復旧に対する信念は、全く揺るがなかった。鉄道が地域づくりにおける要になると確信していたからだ。だから、さまざまな機会を通して、只見線への愛着とマイレール意識の高揚に努め、存続活動につなげてきた。
シンポジウムにパネラーとして参加した加藤夕子さんもその1人だ。4年前に金山町に里帰りした彼女は、「只見線つなぎ隊」を結成し、補助金に頼ることなくすべて自前で土産品開発、展示SLの整備、会津中川駅でのイベントなどに取り組んできた。
しかし、パネラーの津軽鉄道社長の澤田長二郎さんからは、冷静な意見が出された。「これまでの熱意には敬意を表するが、やっとスタートラインだ。乗客が減少一途の津軽鉄道では、ストーブ列車など毎日何か仕掛けている。そうしないと、地域から見放される」と。
また、パネラーの元山形鉄道社長野村浩志さんからは「上下分離の上と下の間に、旅行代理店、広告代理店、総合商社機能を持つ中間支援組織をつくるべきだ。(D)どんと(M)儲けよう(O)奥会津だ」というダジャレを交えた具体的な提案もあった。
これに対して、地元代表の加藤さんからは「復旧が決まったので、今後はただの応援団ではなく、只見線を核として地域全体を盛り上げる事業体をつくりたい」という決意が披歴された。まさに、只見線の新たなページに踏み込んだ歴史的なシンポジウムだった。
これまで鉄道存続を訴え、シンポジウムのコーディネーターを務めた筆者としても、全面復旧が奥会津の豊かな地域づくりにつながるように引き続き関わるつもりである。それは只見線の帰すうが廃線の危機にある北海道などの鉄道のあり方を左右すると考えるからだ。
(大正大学地域構想研究所教授)