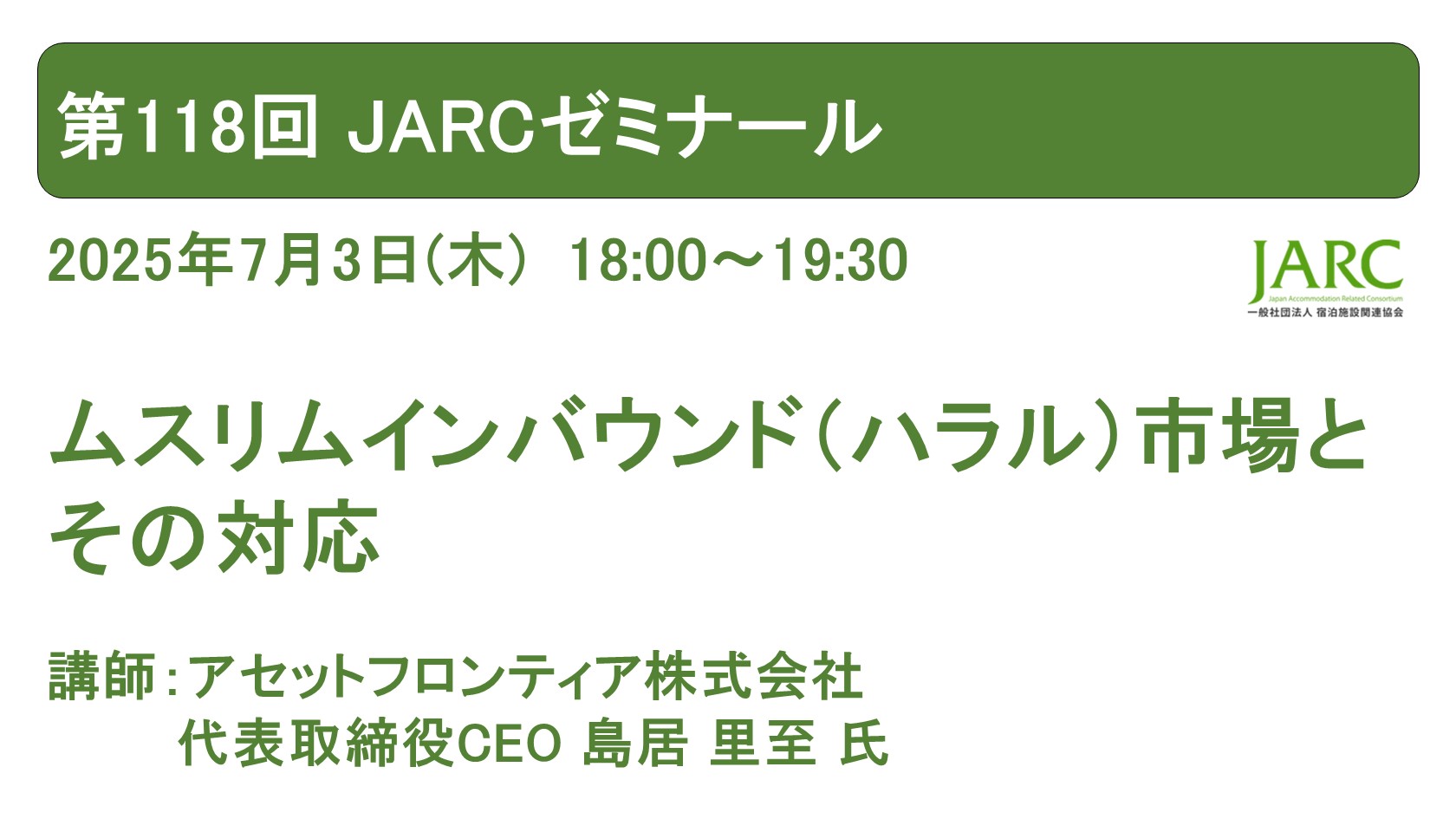「収益性の確保―損益分岐点を引き下げる」のテーマのもと、前回は「付加価値を意識する経営」ということについて述べた。今回は、その大本となる価格設定について考えたい。
(3)価格設定は経営そのもの
旅館業において、高付加価値化↓高収益経営を目指すための「起点」は、「高料金化政策」にある。さらに言い切るなら、高付加価値化↓高収益経営を目指すための「出口」もまた、高料金化政策しかない。
「価格は最高の経営方針」と言われる。さまざまな経営活動の仕組みや成果は価格に集約される。そして結果としての経営体質を方向付けるのも価格だ。
また、こうも言える。客数は営業活動の成果であり、戦術レベルの「努力」だが、価格は戦略レベルの「判断」であり、これを決めるのは経営者の仕事である。
高料金化といっても、どこもがいきなり高級旅館を目指すべきなどと言うつもりはない。それなりの「妥当な範囲」というものがおのずとあり、またどれくらいの価格帯の商売をしていくか、ということは、先ほども述べたように「経営方針」であり「戦略」なので、いろんなゾーンがあってしかるべきである。にしても、自社の損益構造の組み立てとして、しかるべき収益が見込める付加価値の確保↓それを考えた値付けや価格操作を、もっと意識していきましょう、ということだ。
言うまでもなく、ただ価格を吊り上げればよいという簡単な話ではない。その価格で買ってもらえる商品である必要がある。
これまで多くの旅館が、どちらかというと、自館の現状や競争相手との位置関係に照らしながら、「これくらいが妥当なところだろう」という値決めをしてきたかと思う。それはそれで必要な商売感覚だ。
ただ問題としたいのは、そこに戦略思考に基づく「経営意思」が載せられていたか、ということだ。つまり、「経営をこのようにしていきたい↓そのためにはこの価格で売っていきたい(いくべきである)」ということが意識されてきたかどうかである。
商品力と収益力は「ニワトリと卵」のようなもので、互いに因果関係にある。価格設定は商品力から収益力へと向かう矢印の中間にあるが、同時に「この価格で売るための商品はいかにあるべきか」という逆向きの思考を持つこと、そのような経営の構図を描いていくことが大切だと考える。
あるべき価格を描く
←
それにふさわしい商品像を描く
←
現状とのギャップを認識する
←
しかるべきテコ入れを意識する
ここでいう「商品像」とは、施設のことだけではない。料理やサービスだけでもない。最終的にはそれらすべてである。しかしそのどこにも「入り口」はある。それが「付加価値を載せる発想」ということだ。
(リョケン代表取締役社長)