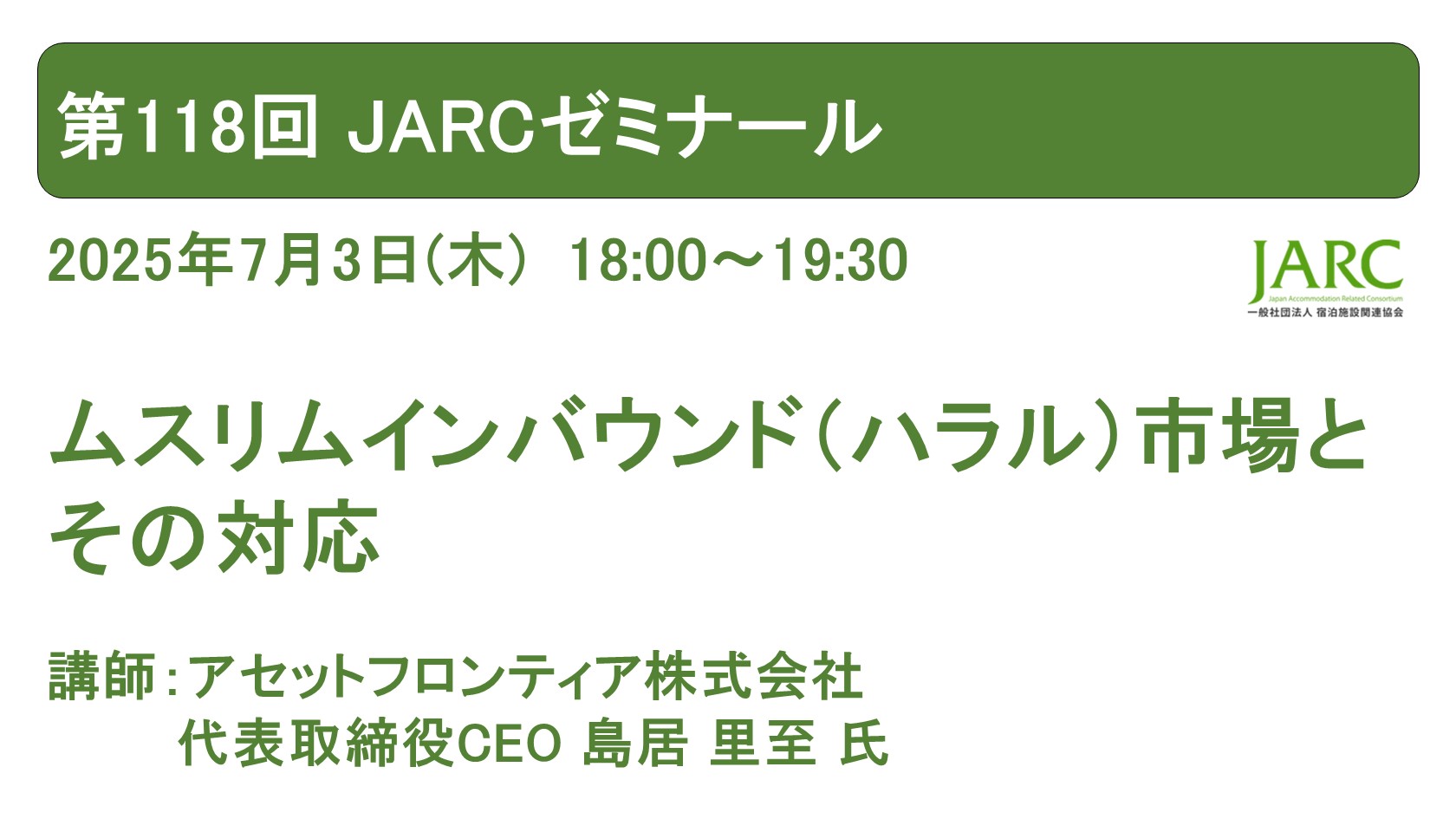一方、「オーダーメイド型」の旅行を定着させるには「商品(素材)」側の変革も重要で、高速バスを含むバスサービスのあり方もそこに含まれる。
まず、「地元(地方)の人の都市への足」として成長してきたわが国の高速バスは、商品設定が地元在住者向けに特化しているケースが多い。
一見すると観光客の需要が大きそうな目的地へ向かう路線であっても、現地では高速道路本線上またはインターチェンジ周辺の途中停留所(おおむねパーク&ライド駐車場を併設)を経由し、旧来の市街地(官庁街や繁華街)や鉄道駅に隣接するバスターミナルが終点となる。
大型テーマパークやアウトレットモールなどを除けば、観光集客施設や温泉街などに直接乗り入れる事例は多くない。
車両タイプも一般的なものが多い。長距離の夜行路線には、テレビなどで話題になる「超豪華」タイプが導入されているものの、観光客の利用を見込める短・中距離の昼行路線には、華やかな車両が投入されることはほとんどない。
高速バスで頻繁に大都市に出かける、地元在住のリピーターにとっては、旅の気分を高揚させるような遊び心よりも、車内トイレや座席コンセントのような設備や、ちょっとしたシートピッチ(前後の座席間隔)の差など機能面の充実の方が重要だからだ。車内で流れる案内放送や映像も、機能優先の内容だ。
つまり、「観光、旅行と言えばバス」という世間のイメージとは裏腹に、ここまでの高速バスは、観光客の利用を想定したものではなかった。
それでも、鉄道が不便な観光地などへ向かう路線については、他に選択肢もないゆえ観光客の利用も多い。鉄道と競合する路線や都市間を結ぶ路線についても、「もうちょっとだけ観光客の方を向けば新しい需要を見込めるはず」と感じることが多い。
運行ルート(停留所)、ダイヤ、旅行会社や沿線の宿泊・観光施設との関係性、旅の高揚感の演出など、高速バスが工夫すべき点は多くある。
(高速バスマーケティング研究所代表)