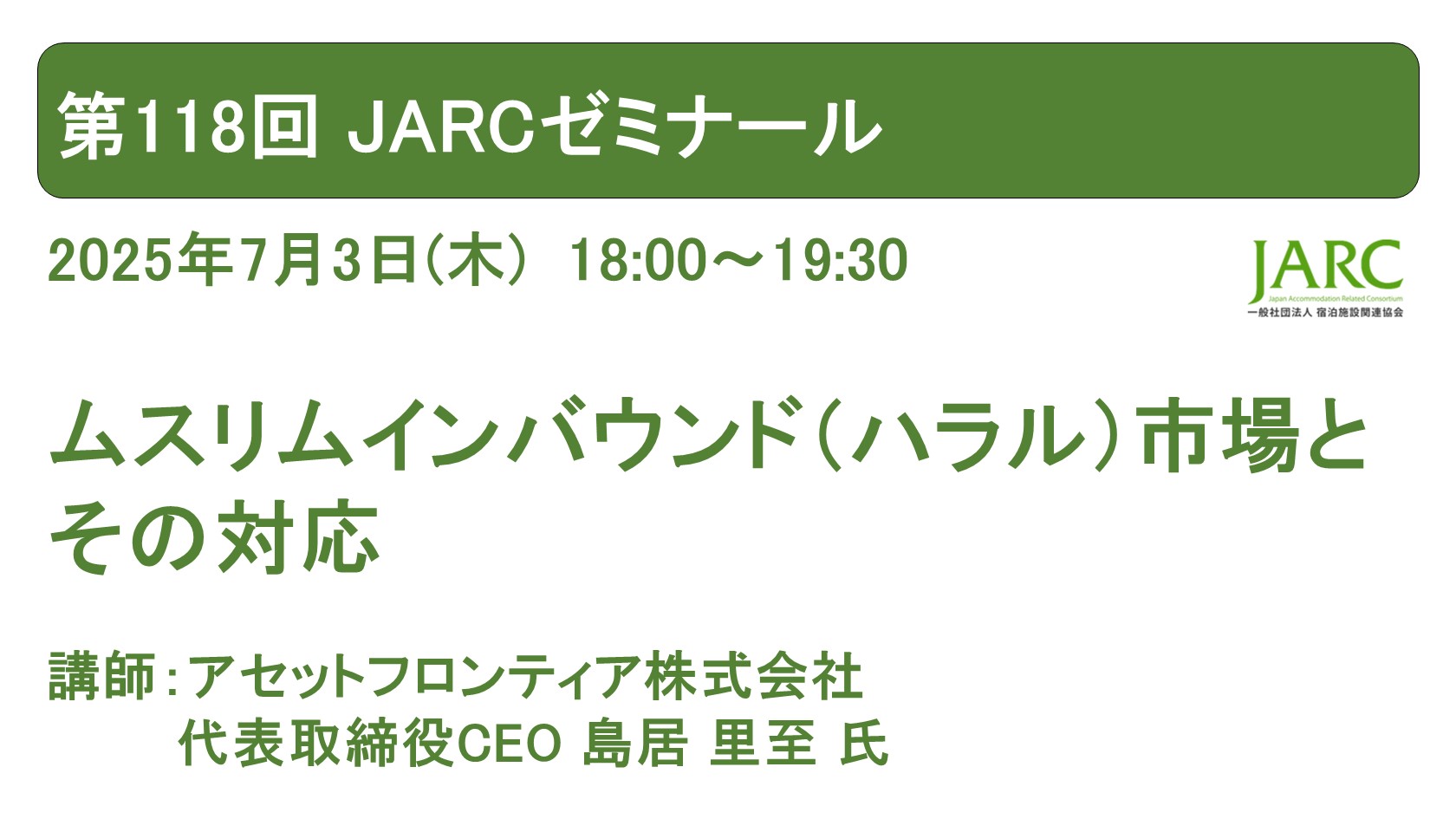一方、一人一人にとって、旅先でしか得られない体験を与えることができなければ、旅行という選択肢を選んでもらえない時代だ。自由に使える休日も、可処分所得も少なく、時間的にも費用的にも効率的なパッケージツアーが有効だった時代はもう終わっている。
旅行者の立場では。
1、「お仕着せ」ではなく、自分自身の興味関心に沿った旅程が組める。また、特定日のみではなく、なるだけ自身の都合に合わせた日や時間帯に利用できる。
2、それでいて、乗り換えの不便さや不安感、時間のロスなどが最小限で済む。
事業者の立場では。
3、全国の観光地に向け、毎日、安定して観光客だけを対象として定期便を運行するだけの市場はないので、明らかに観光需要だけで成り立つ大きなデスティネーションは別として、現行の高速バスにおいてサービスのあり方を見直すことで需要に応える。
4、単なる「移動単品」ではなく、一連の「旅行」の中に位置づけられる
といった、需要側と供給側双方のニーズに対応した商品造り求められている。
実は、難関なのが4の課題であろう。これまで、高速バスの多くは地元リピーターに支えられている。その中で、数少ない、観光客の利用が目立つ路線には共通の特徴がある。
それは、目的地がテーマパークやアウトレットモールなど集客力がある施設、または富士山五合目など人気の観光地である上に、それらの施設や観光地側が、高速バスを公式なアクセスとして認知し自ら告知してくれること。
また、複数地点を周遊するタイプの観光地ではなく、高速バスの単純往復で旅行が成り立つタイプの目的地であること、などである。
つまり「一連の周遊旅行の一部としての高速バス」として位置づけられた成功事例は極めて少ない。
逆に言えば、この課題を克服できれば、もっと多くの路線でニーズに応えることができるはずである。
(高速バスマーケティング研究所代表)