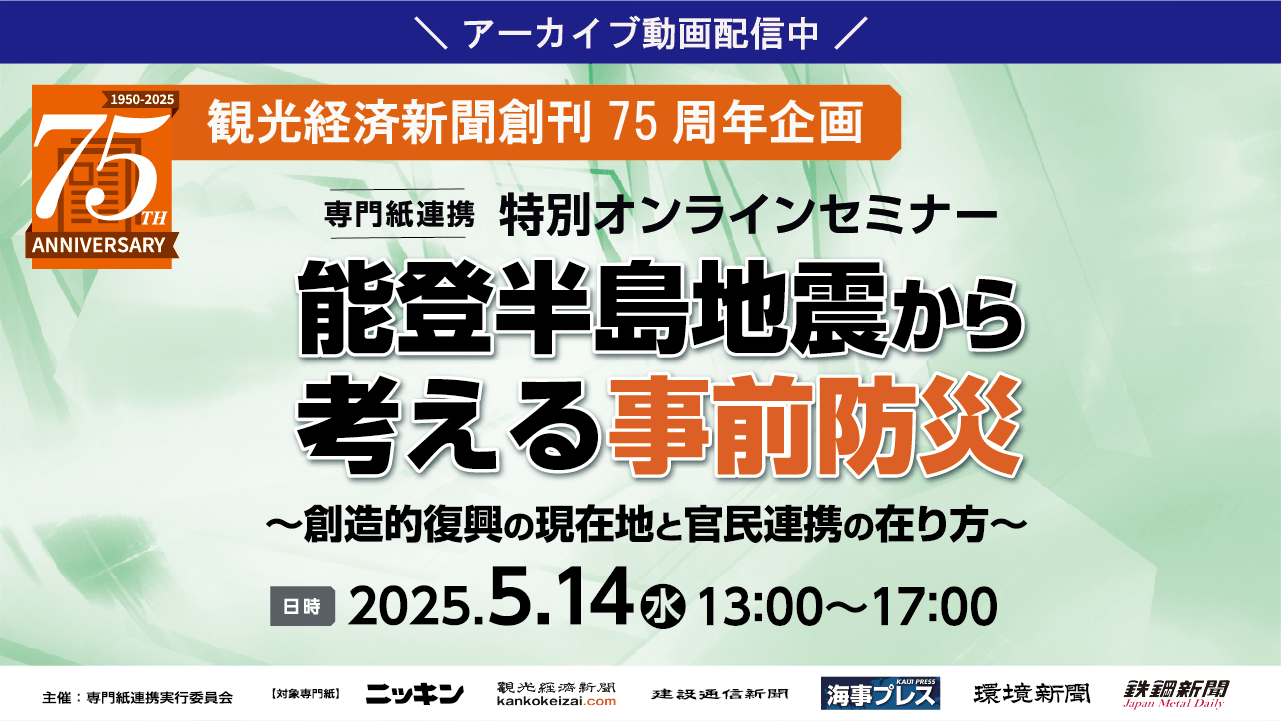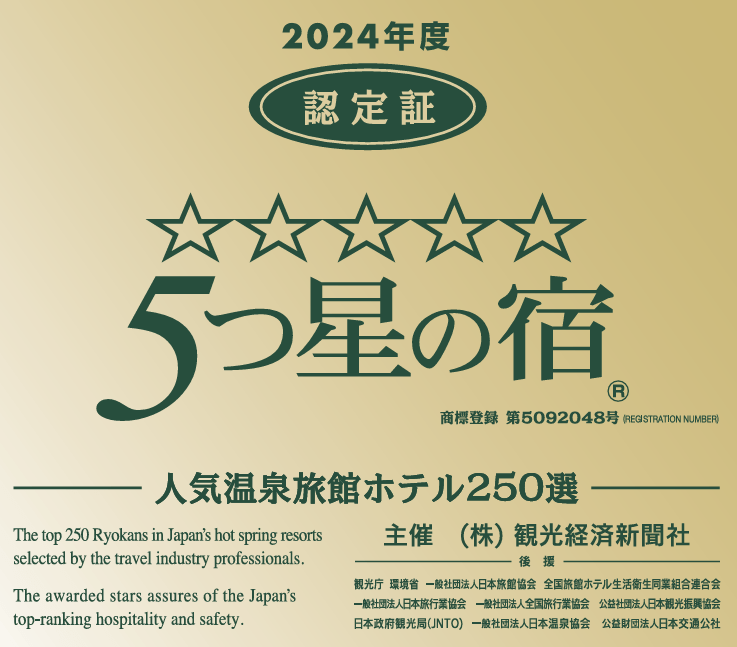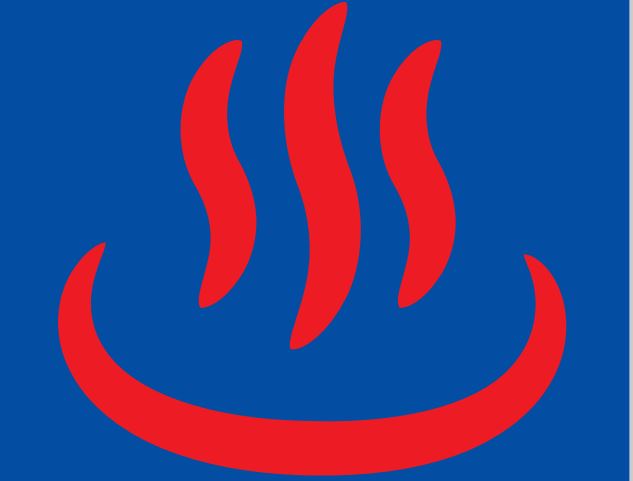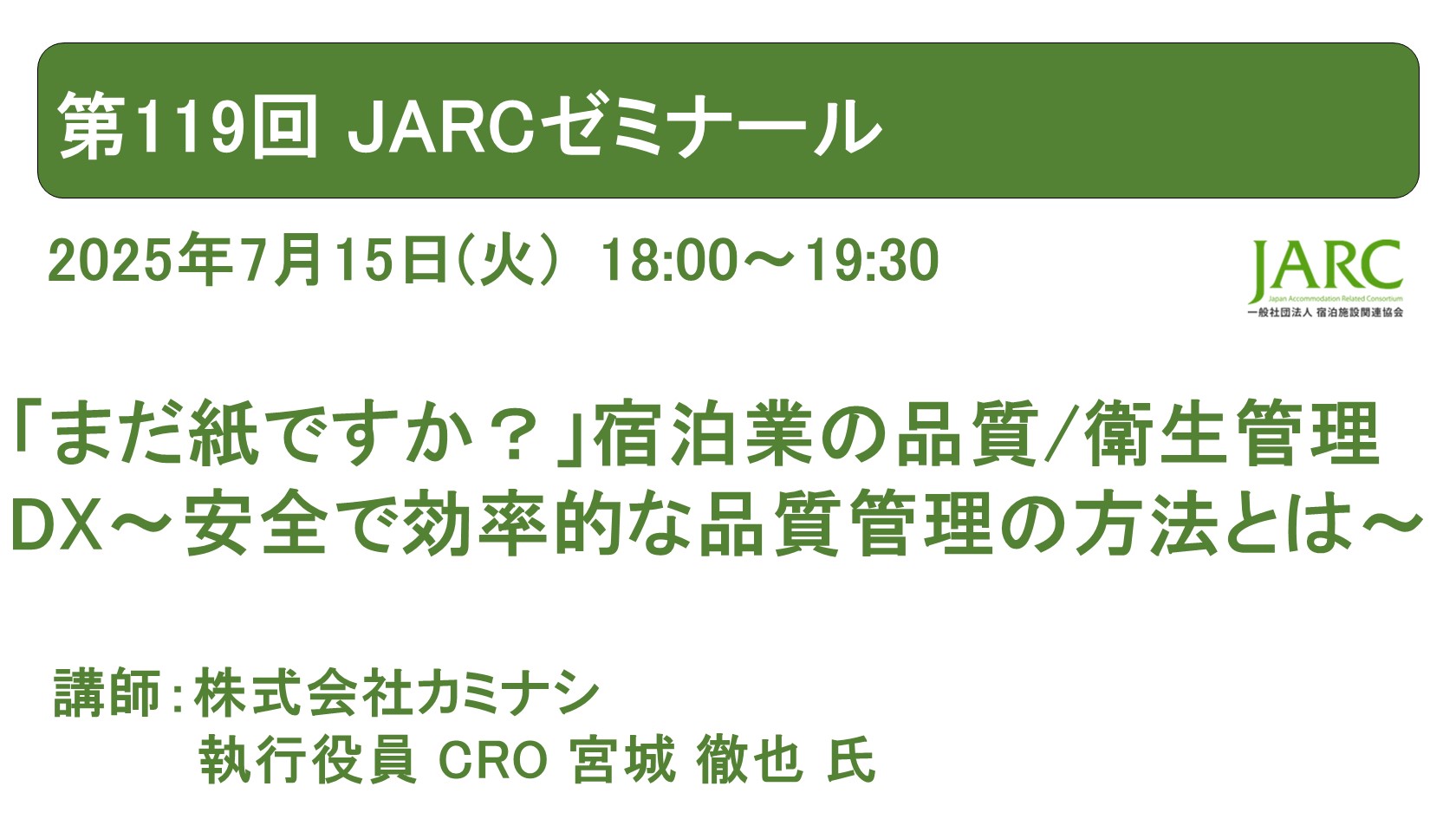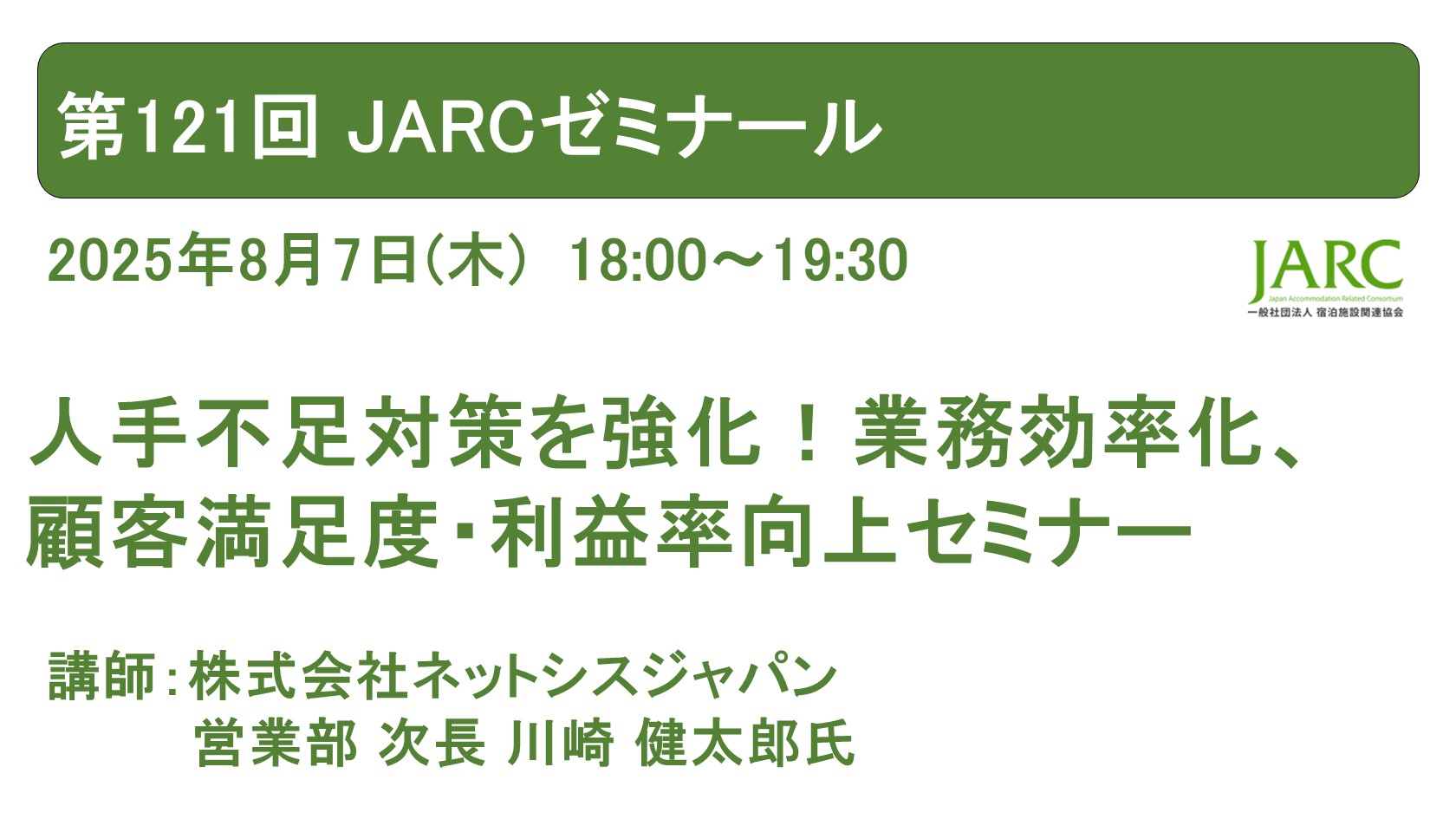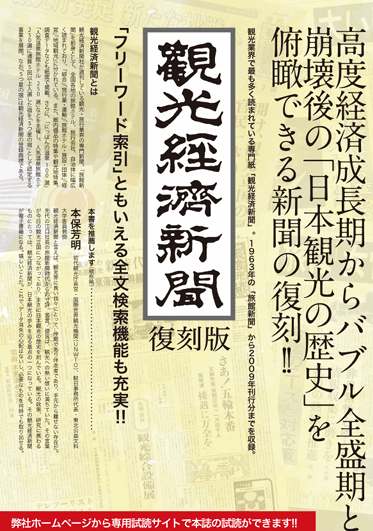「乗客モニター制度」が導入されたことによって、それまで当の乗務員任せであった、日常の乗務(運転および接客)の様子が可視化され、一人一人の乗務員について会社が客観的な評価を行うことが可能になった。
このデータに、軽微なものを含む事故の履歴、遅刻の有無など勤怠の状況、後輩の指導など乗務以外の勤務内容を加味して、乗務員の人事評価となる。
なお、その評価をどれだけ処遇に反映させるかという点については、大手バス事業者の間でも大きな差がある。
賞与査定に利用する程度の会社もあれば、積極的に処遇に活用し、同じ勤続年数の乗務員同士でも基本給に大きな差をつけたり、「班長」「リーダー」といったタイトルに反映させたりする事業者もある。
職能と役職を分離し、昇給は絶対評価をもとに、昇格は相対評価をもとに処遇するという、大手一流企業の人事評価制度並みの複雑な運用を行っている事業者もある。
このような乗務員の人事評価制度が導入された事業者では、どちらかといえば「一匹狼」という色もある「職人」という扱いであったバス乗務員という仕事に、サラリーマン的な要素が大きくなった。
会社側から見れば、従業員管理と業務標準化に寄与したことは間違いないであろう。特に、接客態度について、乗客からの苦情は大きく減少したはずである。
これらの制度が、大手事業者を中心に1990年代後半から導入され、2000年以降に普及したのは前述の通りである。
バブル経済崩壊後、三大都市圏の大手私鉄のバス部門は分社化が進み、バス事業単体での収益を求められるようになった。その代わりに、給与テーブル(基本給の額など)や人事評価において、鉄道とは切り離しバス独自の制度を導入することができるようになったことが背景にある。
そういう経緯を持つゆえ、これらの人事制度には、限界や課題が残されていることもまた確かである。
(高速バスマーケティング研究所代表)