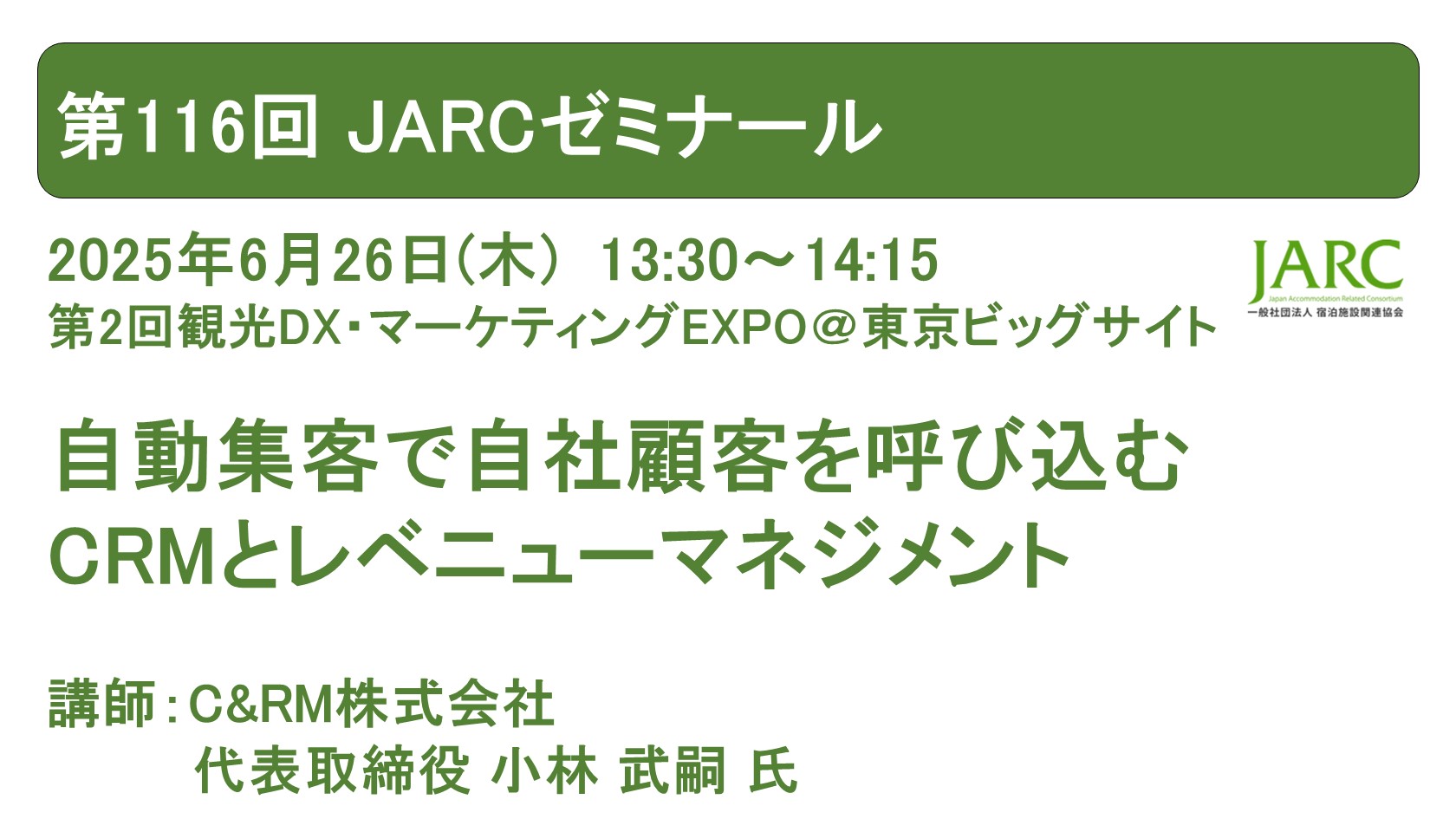大型バスの車内のトイレを近隣住民に開放。手書きの張り紙で案内した(2016年4月、熊本市)
2016年4月の熊本地震では、バスが機動力を発揮し、地域の早期復旧を後押しした。
九州産交バス(熊本市、岩崎司晃社長=熊本県バス協会会長)の営業所のうち、益城町に構える木山営業所は、震度7の激しい揺れに襲われた。ドライバーを含む多くの社員の自宅が全半壊の被害を受けた。管轄エリアは熊本都市圏の東部。道路は数週間にわたって不通に。一部開通した後も、路線バスの運行は建物の倒壊や道路の損傷により、すぐに再開できなかった。一時、小回りの利くワンボックス車を無償で走らせた。
車両の被害では、駐車中のバス同士が揺れで接触し、側面が大破したり、昇降口のステップ(踏み板)が破損したりした。
上村健児・取締役管理本部長は、「社員に死傷者はいなかった。ただ、震源地の木山営業所に勤務する社員の家は著しい被害を受け、とても住める状態ではなくなった。仮設住宅などに散り散りになってしまった」と被災直後を振り返る。
地震の衝撃は熊本市内の公共交通にも色濃く出た。「最も解決が難しかったのは渋滞だった」と上村氏。全国の政令指定市の中でも、熊本は元々、深刻な渋滞で知られる。「道路の欠損や物資輸送のトラックの影響が大きかった。路線バスは定時性が守れなくなり、『バスで行ったら遅れる。当てにならん』と言われ、通勤の足が自家用車に移ってしまった。当然、さらに渋滞する悪循環だ。バスは10%の間引き運行を実施した。観光客もいなくなり、輸送人員は減少した」。
都市間の高速バスは、高速道路の開通状況に応じて徐々に再開させていった。
また、運行にとどまらず、地域の一企業としての社会貢献にも努めた。トイレを備えた大型観光バスを本社営業所の前に置き、住民に開放。「トイレ」「女子専用」などと手書きされた張り紙を掲示して案内した。水道が止まった家庭に多く利用されたようだ。
◇
大地震の経験は、被災地でのバスの役割と価値を再認識する契機になった。
上村氏は「鉄道は、路線が寸断されれば、インフラが回復するまで相当の時間がかかる。
その点、バスは運行ルートを柔軟に変更できる。実際、応急の仮設住宅が造られた際は、ルートを替えて入居者の足を支えた。九州運輸局や県、市からのさまざまな依頼に機動力を持って応え、『バスは地震に強い』ことが証明された。今後、大きな災害が起きても、エッセンシャル(必要不可欠)な仕事として役割を果たす」と覚悟している。
同社は震災後、事業継続計画(BCP)を策定した。震度5強以上が起きた場合、部長以上の管理職が本社に参集し、対策本部を立ち上げ、緊急の運行体制を構築する。ハード面では本社に発電装置を導入した。一部の営業所には食べ物や水の備蓄倉庫を設けた。「橋や道路の崩落などでライフラインが絶たれても、1週間程度は活動できる」と見ている。
(東京交通新聞)

大型バスの車内のトイレを近隣住民に開放。手書きの張り紙で案内した(2016年4月、熊本市)