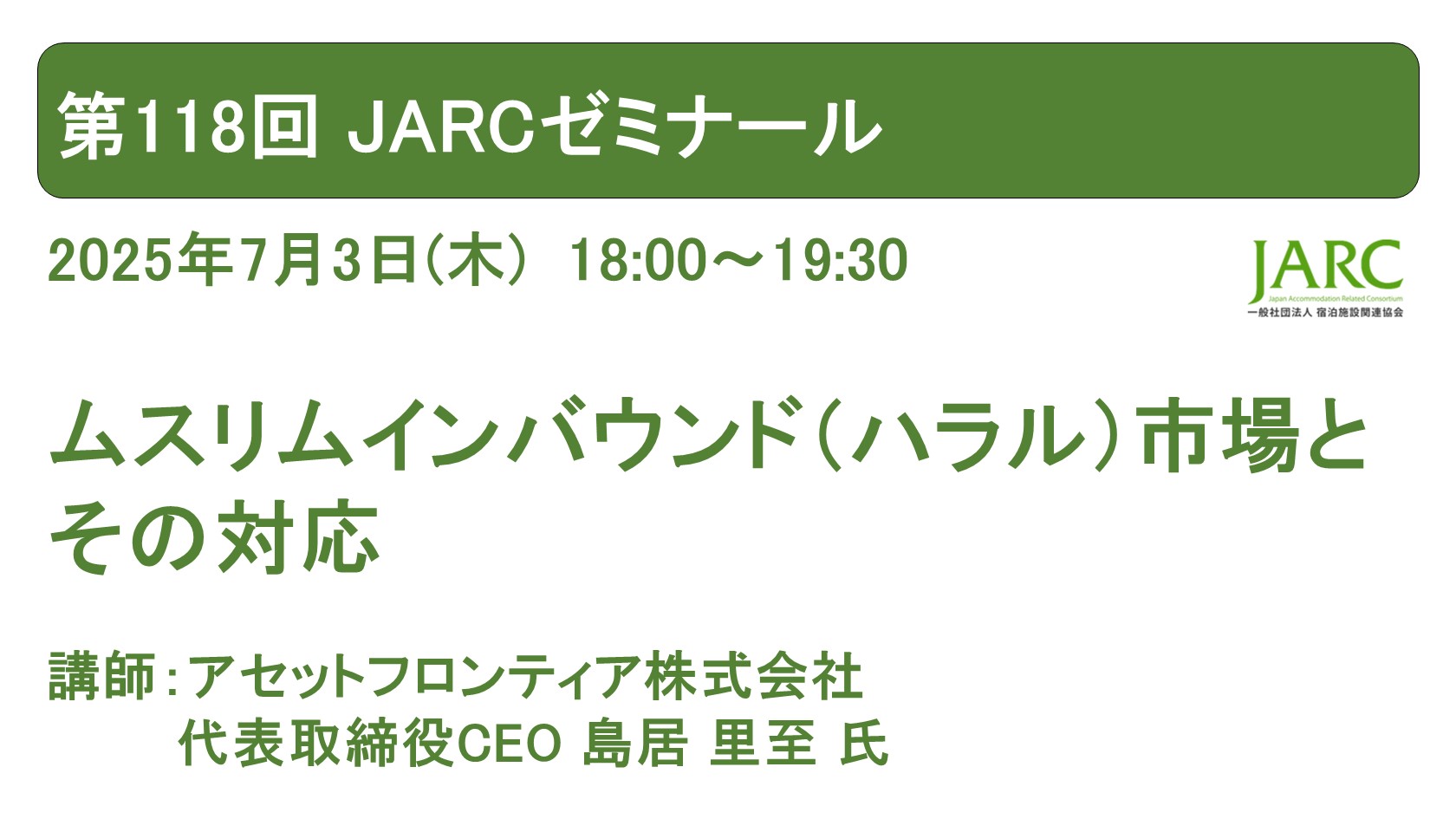旅館業においても労働生産性の向上と効率化は大きな課題である。だが、やみくもに人員を削減しサービスを合理化してしまっては、旅館業が担い、培ってきた日本のもてなし文化を衰退あるいは消滅させてしまう危険性も否めない。実は、その兆候は、すでに随所に見られつつある。
例えば、新入社員に煎茶を入れるときに使用する道具類について名称を尋ねたところ、誰一人として全ての名称を正しく答えることができなかった。「湯のみ」は「コップ」、「茶托」は「茶コースター」、「茶こぼし」に至っては名称どころか使い方についても全く想像することができなかった。
12、13年前までは、宿泊客が到着すると担当係が客室備品の茶器を使ってお茶を入れて差し上げるのが一般的だった。そこには、一服のお茶で長旅の疲れを癒やしてほしいという思いがあった。
それが、人手不足と業務効率化の観点からロビーで茶菓を振る舞うようになり、いまでは「フリードリンクでお好きなものをどうぞ」である。旅館の中には呈茶自体を廃止したところもある。
煎茶を入れるにも手順がある。まずは、ポットの湯を湯のみ茶碗に入れ、器を温める。次に、湯のみ茶碗の湯を、茶葉を入れた急須に注ぎ入れふたをして茶葉を蒸らす。茶葉を蒸らしている間に、客と会話を交わし、会話の中から顧客ニーズを探っていく。茶葉が十分に蒸れたら、人数分の湯のみ茶わんに、お茶の色が均等になるよう上座側から3回程度に分けて少しずつ注ぎ入れる。その後、右手で茶托の柾目(まさめ)(木目のこと)が横向きになるよう左掌にのせ、その上に湯のみをセットする。
全ての湯のみを茶托にのせたら、最初にセットしたお茶を茶托の柾目を横向きにしたまま上座席から順に提供していく。なお、木は木目に沿って縦に割れるため、柾目を顧客に対し直角に置くと「切腹」をイメージさせるのでNG。
この一連の動作を指先まで神経を行き渡らせながら、美しい所作で行っていくところに、もてなし文化の原点がある。たかが呈茶、されど呈茶である。
ほかにも20~30年前までは「浴衣合わせ」「靴下洗い」という気遣いがあった。
当時の宿泊客は8、9割が男性の団体客で、顧客が到着すると接客係は客室に出向き、浴衣を客の背中にあてて着丈を測りジャストサイズの浴衣を用意するのである。また、顧客が履いてきた靴下を手洗いして翌朝、客室に届けるサービスも行っていた。ちなみに、宿の係が宿泊客の足を洗う「足濯ぎ(あしすすぎ)」は江戸時代、東海道沿いの旅籠でも行われており、昭和の「靴下洗い」は、この名残かもしれない。
このように、時代の流れとともに消滅してしまった旅館のおもてなしは少なくない。日本旅館のもてなし文化を丹念に探り、それを変遷記録として書き留めておくことも研究者としての使命だと考えている。
福島 規子(ふくしま・のりこ)九州国際大学教授・博士(観光学)、オフィスヴァルト・サービスコンサルタント。