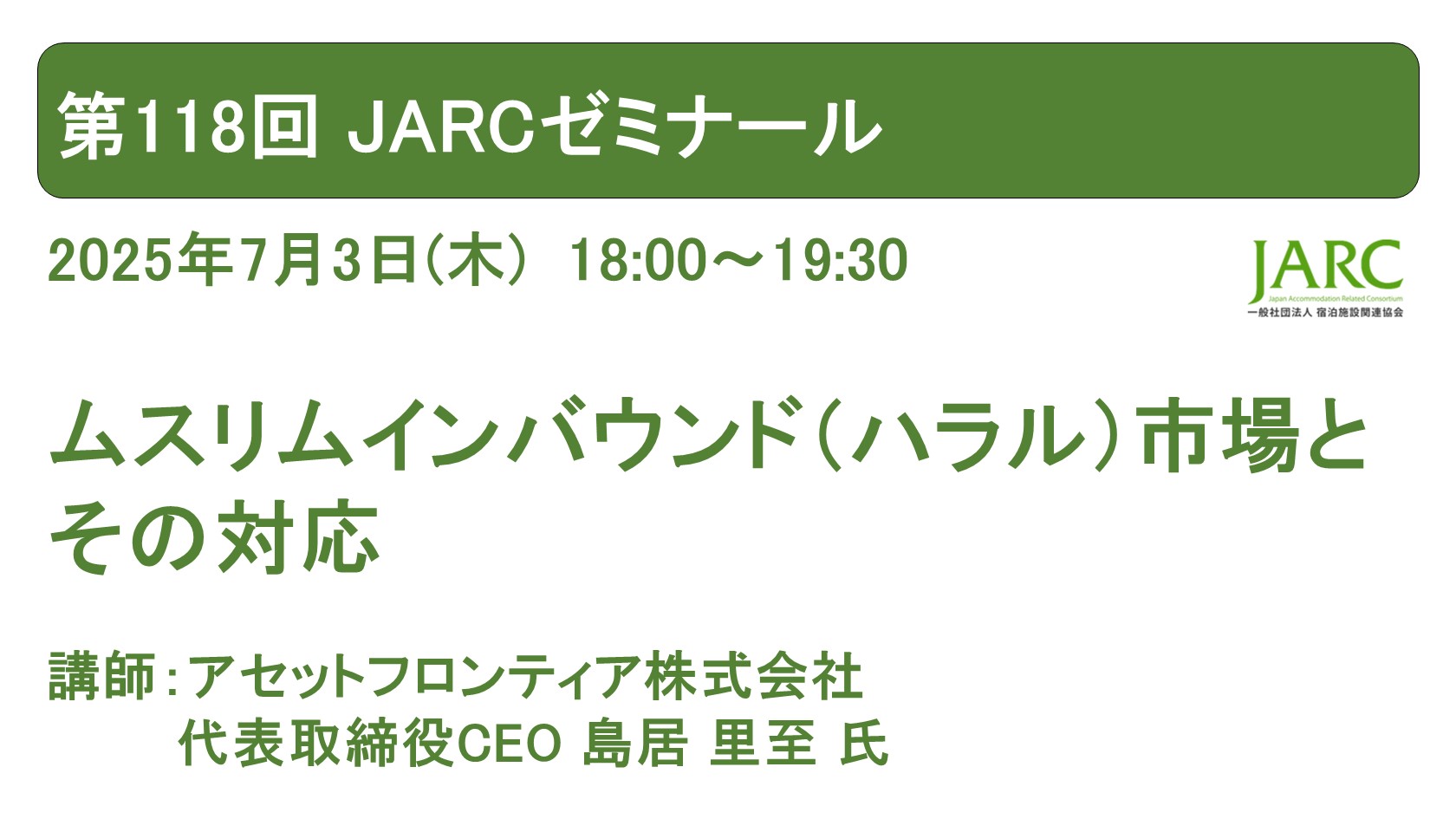松浪氏
大人に成長するにつれ、多くの人たちにお世話になる。私はオリンピックを目指すレスラーだった。たくさんの指導者からさまざまなアドバイスを受けた。レスラーだった私の人生を決定づけてくれたのは、レスリングの父ともうたわれた故八田一朗氏(当時日本レスリング協会長)。“八田イズム”で日本を世界の強豪国に育てた強烈な指導者であられた。
私がアフガニスタンの国立カブール大学の教員になったのは、八田会長が国際交流基金に推薦してくれたからだ。八田会長は、1米ドル360円の時代であるにもかかわらず、「国際人になれ!」が口グセであられた。で、私はレスリングの実力のおかげで、州立東ミシガン大学に特待生で留学することができた。
八田会長には、2人の息子さんと1人の娘さんがおられた。3人とも米国で暮らしていて、会長は奥さまと2人で東京・広尾に住んでいた。愛犬の豆柴犬に芸を教える調教を毎朝楽しんでおられた。俳人でもあられ、「狩の犬、獲物を追って、どこまでも」の句を忘れない。句集まで出されるほど文化人でもあられたが、肝硬変で鬼籍に入られた。
そして数年後、1人暮らしの奥さまは自宅で亡くなられた。ところが、発見が遅れた。それで私は、1人暮らし、特に高齢者の1人暮らしは恐いという現実を学んだ。加えて、3人の子供たちが財産を巡って闘うこととなる。私たちの目には、悲劇と映ったが、遺言書がないとトラブルを招来させて当然であろう。立派な子供たちを持っても、親が1人暮らしをしていると難しい問題が起こる。
たとえ1人暮らしであっても、身寄りのない人の場合、果たしてどうなるのだろうか。身寄りがあっても多岐にわたる問題が生じる。新潟県魚沼市が、2020年11月に「身寄りのない人への支援に関するガイドライン」を策定した(毎日新聞、滝野隆浩の掃苔記)という。魚沼市のこの積極性を評価すべきであり、他の自治体も続くべきであろう。1人暮らしの高齢者は、間違いなく全国で増加しているのだから、自治体が対応するしかない。
1人暮らしだけならともかく、その人が認知症であったり障がい者であったりした場合、憲法の保障する「最低限度の生活」もできなくなる可能性が高い。私たちが想定する諸問題のほかに、その人独特の問題を抱えている一面もある。孤独な生活を営んでいると、人間はどうしても心身ともに閉鎖的に陥る。この人たちへのサービスを盛んにして、1人暮らしの寂しさを緩和させる必要がある。
孤独死が問題になろうとも、自治体は手を打たない。1人暮らしが増加の一方、遠慮がちな高齢者を無視することなく、各自治体は魚沼市のようにガイドラインを策定したり、条例を作ってほしい。デジタル化が進む社会、スマホの使用もままならない高齢者も多い。しかも体調の変化も早い。平均寿命が伸びたとはいえ、まだまだ健康寿命が伸長されているわけではない。重厚な1人暮らしの高齢者へのサービスをお願いしたい。「高齢者サービス日本一」を競う自治体の登場を期待する。
元気な高齢者から、さまざまな事項について質問しておき、その人の意志をきちんと理解しておくべきである。自治体は社会福祉協議会に丸投げせず、協働して高齢者サービスを行う、老人を大切にする自治体であってほしい。で、その高齢者の人権を守る必要があろう。
75歳に達すると、いよいよ後期高齢者となり、新しい健康保険証が送られてくる。住んでいる住宅問題、金銭の管理等、だんだんと考えねばならなくなる。相談相手のいない孤独な高齢者では困り果てるばかりか、何も考えない高齢者もいる。私たちは、常に最悪のことを思考する危機管理を心しておかねばならない。社会状況が毎年のごとく変化する。
その変化に自治体が対応する。家庭内の電化製品にも変化がある。劣化しても当然である。高齢者の1人暮らしは、あまりにもリスキーだ。自治体の親切な手助けが求められている。