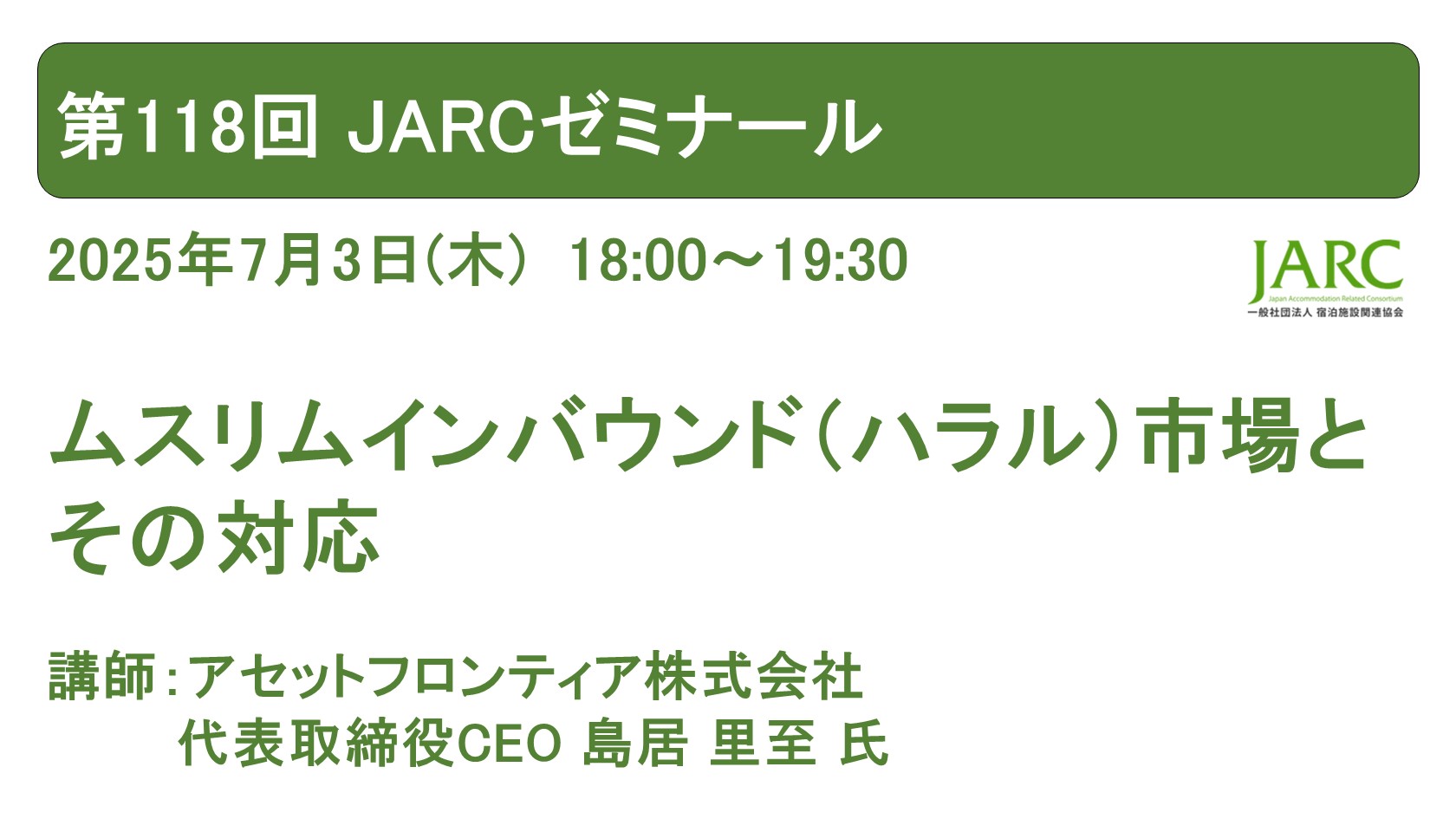竹内氏
前号で、防腐効果やデンプンの老化防止効果など、砂糖がもたらすさまざまな効果について述べたが、砂糖の力はまだまだたくさんある。
メレンゲや生クリームを泡立てる際、砂糖を加えると、泡の水分を砂糖が抱え込むため、泡が消えにくくなる。最近、泡立ててメレンゲ状にした卵白をご飯に載せ、卵黄を最後にトッピングするTKG(卵かけご飯)がはやっているが、手動だと結構大変だ。でも、砂糖を少々加えれば、ずっと楽に泡立てられるハズ。
おいしそうな焼き色も、砂糖のおかげだ。食材に含まれるアミノ酸と糖が、加熱調理によって化学反応を起こし、褐色物質であるメラノイジンや香味成分を生成する。いわゆるメイラード反応ってヤツだ。パン生地は白いが、天火加熱するとキツネ色に焼き上がり、香ばしい匂いが食欲をそそる。コレも砂糖の力。
パンを膨らませるのも、砂糖が必要。パンは発酵で生まれる炭酸ガスによって膨らむが、砂糖を加えると酵母の働きが活発になり、ふんわり膨らむという。
砂糖には、油の酸化防止効果もある。例えば古くなったポテトチップスがマズイのは、油が空気中の酸素の影響を受け劣化するから。クッキーなど甘いお菓子は、砂糖が油の中の水分と結合して酸素が溶け込みにくくなり、劣化しにくい。
これだけいろいろなことをこなしてくれる、便利な砂糖。一体いつ頃から人類の味方になってくれたのか?
砂糖の原料であるサトウキビの原種は、紀元前1万5千~8千年ごろ、ニューギニア周辺で誕生したとされる。その後、紀元前400年ごろまでに、インドで砂糖が作られたようだ。アレクサンダー大王のインド遠征を経て中東に広まり、十字軍遠征によってヨーロッパにも伝わった。大航海時代には新大陸にサトウキビがもたらされ、大規模栽培が始まったという。
日本には、奈良時代に唐の僧侶鑑真によって持ち込まれたらしい。当初は薬として扱われていたようで、貴重品であった。室町時代の日明貿易で砂糖の輸入が盛んになり、戦国時代に南蛮貿易が始まると、金平糖やカステラなどの南蛮菓子がもたらされた。江戸時代、将軍吉宗がサトウキビ栽培を奨励、砂糖づくりが広まったとされる。
日本の砂糖黎明期、琉球や奄美大島で作られたのは、糖液を煮詰めた黒糖だ。不純物をろ過し精製したのが白糖で、精製する途中で煮詰めた物がきび砂糖。一方、独自の進化を遂げたのが「和三盆」。香川県讃岐和三盆の伝統製法では「押し船」という型に入れ重しを載せて糖蜜を抜き、職人が手でもみほぐす「研ぎ」という工程を経て、また押し船、研ぎと繰り返して白くするという。お盆の上で3日間研ぐことからその名が付いたとされ、製造には約1週間掛かるそうだ。
調べたら、かなり深遠な砂糖の世界。植物だけが光合成で作り出せるショ糖を、われわれが砂糖として使えるのは、先人の努力の賜物だ。…ちょっぴり疲れたから、甘い物食べちゃおう♪
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。