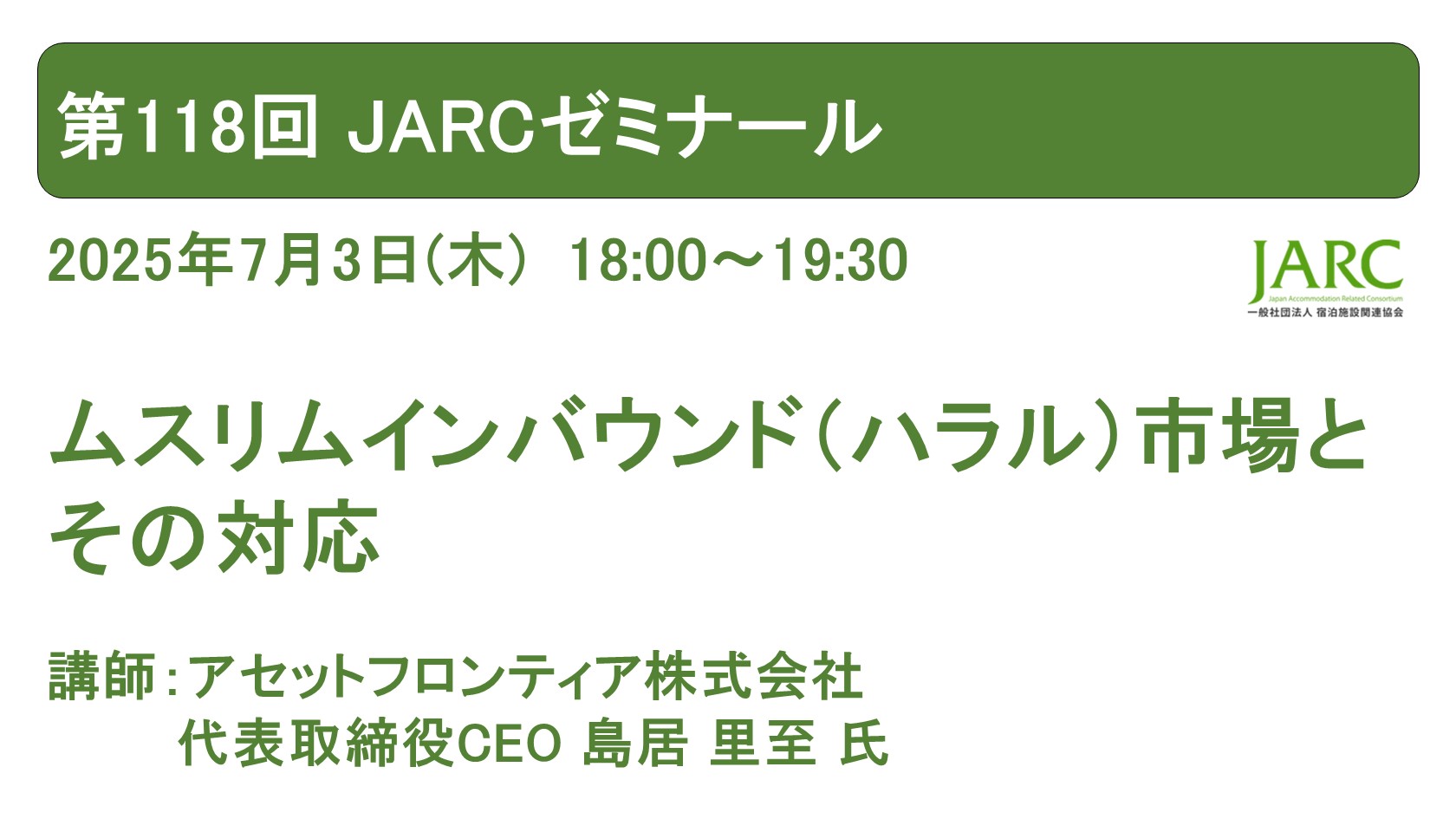JR西日本の城端線と氷見線は、富山県の高岡駅を起点とする非電化単線のローカル線です。輸送密度はいずれも2千人台。利用者が多いとはいえませんが、地域住民の足として活用されています。
ローカル線にしては比較的本数が多く、終日毎時1本程度が運行。北陸新幹線の新高岡駅も経由するので、新幹線の二次交通の役割も担います。
ただ、北陸新幹線の開業に合わせて、起点の高岡駅を通る北陸本線が第三セクターのあいの風とやま鉄道(あい鉄)に移管されてしまい、他のJR在来線との接続が失われた状態になっています。JRからみると「飛び地路線」になってしまい、効率的な運営ができない状況に陥りました。そのためか積極的な投資も手控えられていて、国鉄時代の古いディーゼルカーがいまだに走っています。
沿線人口は比較的多く、ポテンシャルのある路線です。そこで、地元自治体とJRは、城端・氷見線を活用するためのさまざまな議論を続けてきました。その結論として、両路線をJRからあい鉄に移管し、直通運転をする方針が固まりました。
背景として、地域公共交通活性化法が改正され、鉄道事業を「再構築」する場合の補助金が最大50%に引き上げられたことがあげられます。この制度改正により、自治体は、国の大きな支援を受けながら新型車両などを導入することができるようになりました。
ローカル線をJRが運営する場合、地元は原則として費用を負担しなくていいですし、安心感もあります。ただ、JRは民間企業なので、もうからない路線への投資は手控えられ、利便性の向上より赤字の削減に重点が置かれてしまいます。そのため、住民が使いにくく、利用者が減るという悪循環に陥りがちです。
ローカル線を地元の三セクに移管すれば、自治体の負担は増えますが、地域の都合に合わせて利便性を高められます。国鉄車両を最先端の蓄電池車両に切り換えることもできますし、交通系ICカードを導入することもできます。地域の三セクと一体運営になることで、ダイヤ調整もしやすくなるでしょう。地域で鉄道を維持すると決断すれば、費用はかかりますが、使いやすくなるのです。
全国各地のローカル線で、存廃を含めた議論が浮上しています。城端・氷見線の事例が、今後の先行的な取り組みとして注目されるのは間違いありません。
(旅行総合研究所タビリス代表)