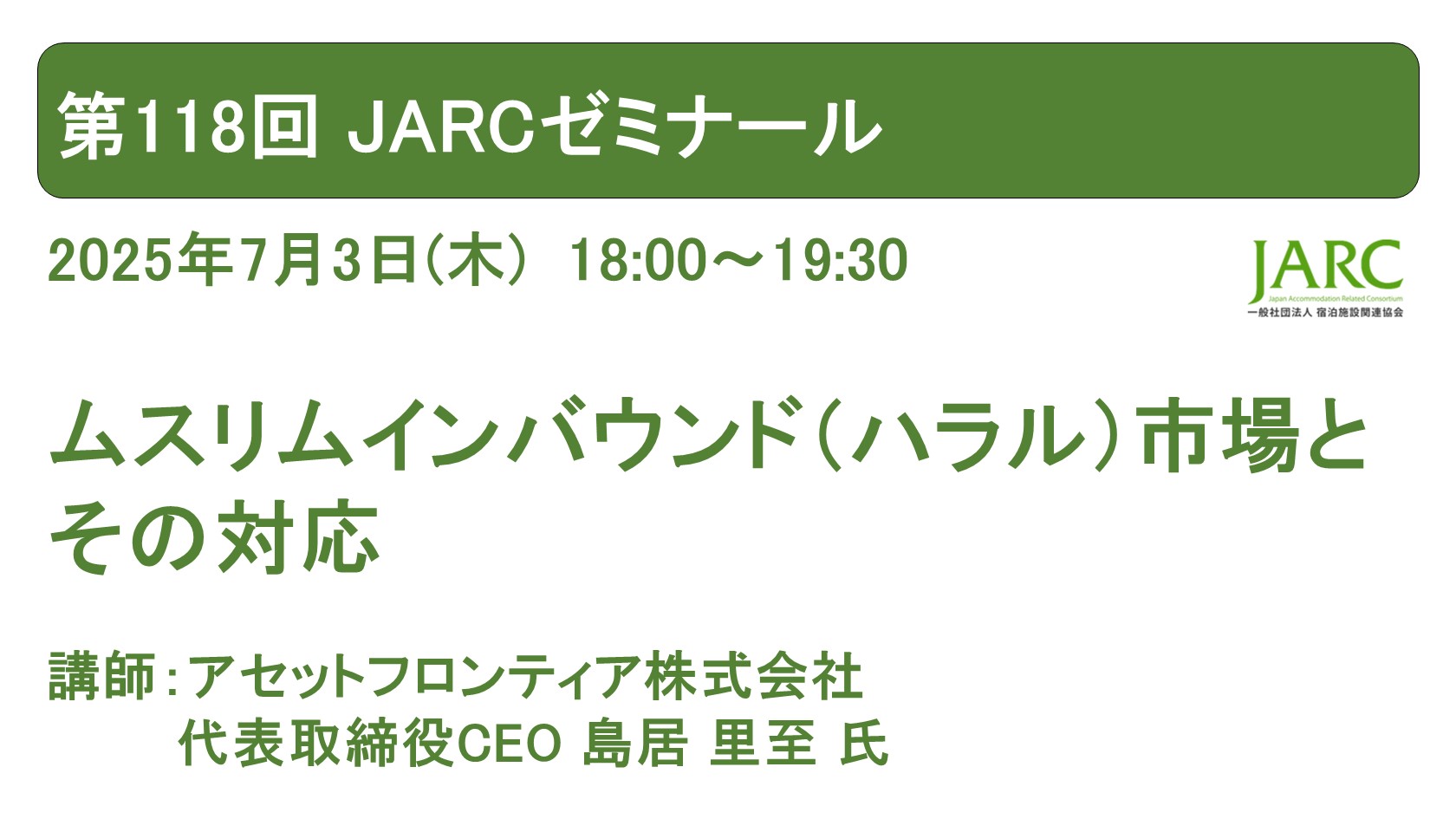少子化が労働人口減少の問題となる中で、労働力不足はホテルや旅館など宿泊施設の主翼をなす事業において深刻になってきている。
今年4月1日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行され「1号特定技能外国人」の受け入れが可能となる。ホテルのフロント業務などは、世界標準的な業務で、海外のホテルやホテル学校で技能研修を行うことが可能であるが、旅館業務の多くは日本独自のものであり日本の文化を色濃く反映している。
昨今、世界中、空港も都市も周囲を見ればどこも同じ景色で、どこの国にいるのか分からなくなる。観光や旅の醍醐味(だいごみ)は異文化との触れ合いである。この醍醐味である異文化と触れ合う機会を与える日本の主たる観光産業は「旅館」であり、神社仏閣と並んで、日本の地域文化を発信する拠点である。
現在、消費は「モノ」消費から「コト」消費へ変わってきているといわれている。
もともと宿泊業は「コト」消費であり、体験、経験など「思い出作り」のサービス業態である。観光においても、消費者の性向は世界的に「モノ」観光から「コト」観光へと推移するであろう。
観光地の風景、買い物、美食を目的とする従来型の「モノ」観光は数回で飽きる。今後、固有の文化に触れ、知識や教養を学ぶ「コト」観光が主力となろう。「写経」「俳句」「和歌」などに興味を持つ外国人も増えてきている。
このような時代に、主役を演ずるのは旅館である。しかし、旅館が単に労働力として外国人研修生を受け入れ、外国人観光客にその母国語の接遇を行うだけで「よし」としていたら間違いなく日本の文化は滅びると思う。
まず、外国人労働者に日本の文化を学んでもらいたい。日本の接客技術は日本人が親から自然に学んだ「心遣い、礼儀、調和」など基本道徳の上あることを忘れてならない。発足した「宿泊業技能試験センター」の技能試験には、日本文化に関する知識、道徳を試験科目に取り入れるべきだと思う。
(NPO・シニアマイスターネットワーク会員 一般社団法人国際観光文化交流協会専務理事 サーブホテルズ株式会社代表取締役、八木豊)