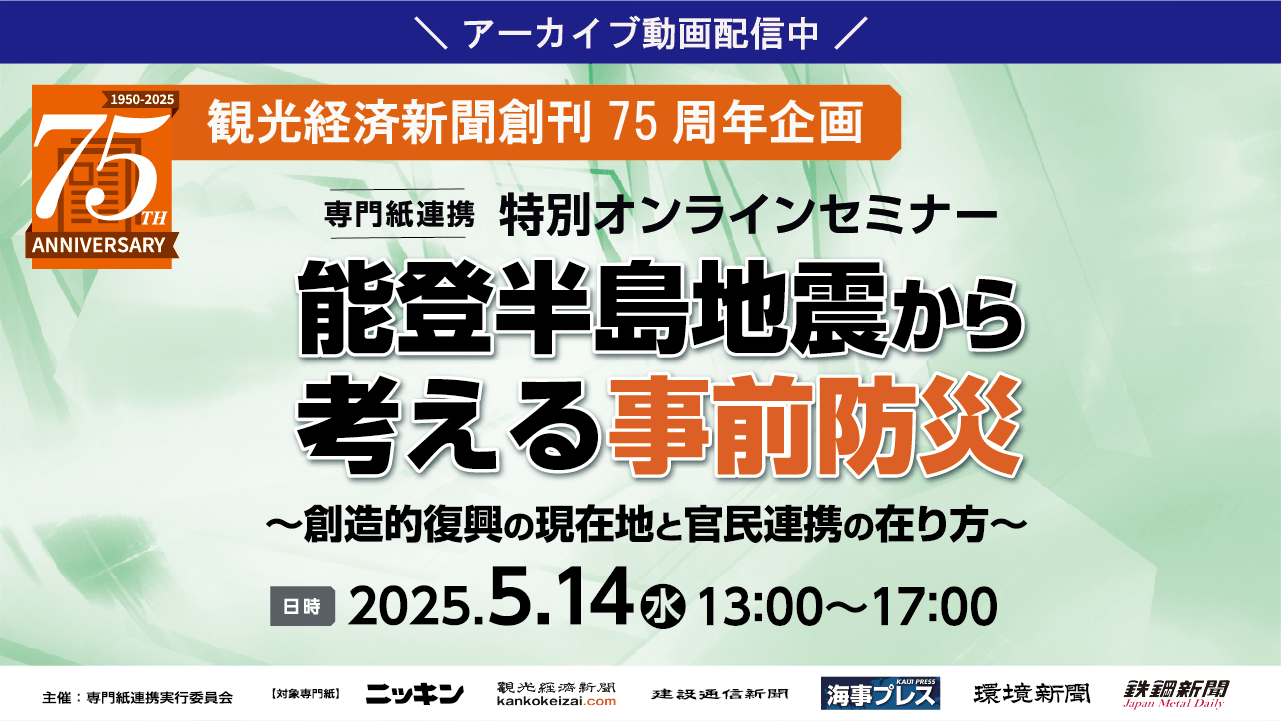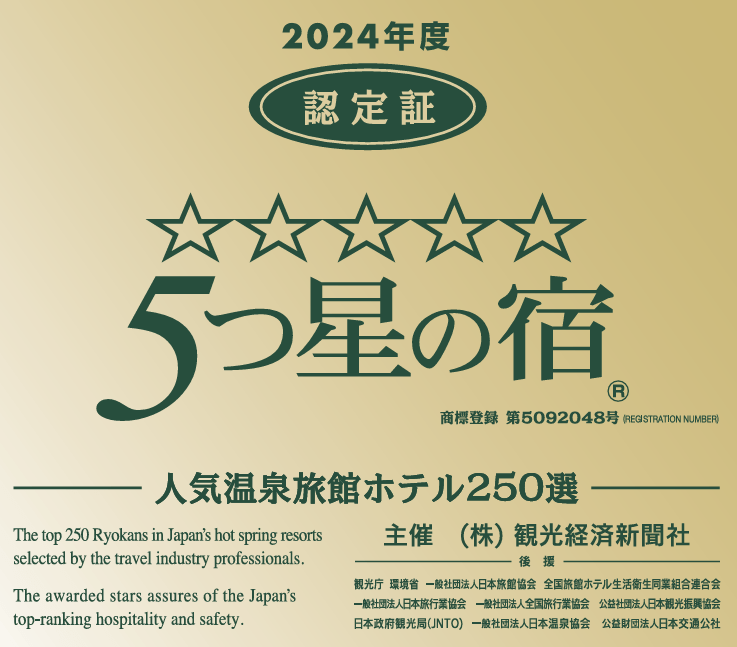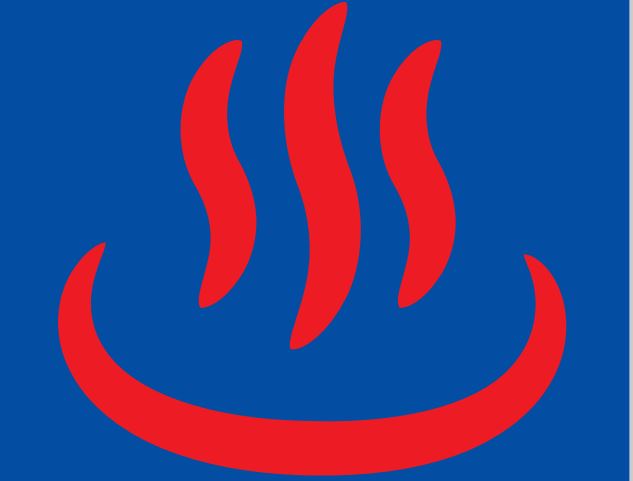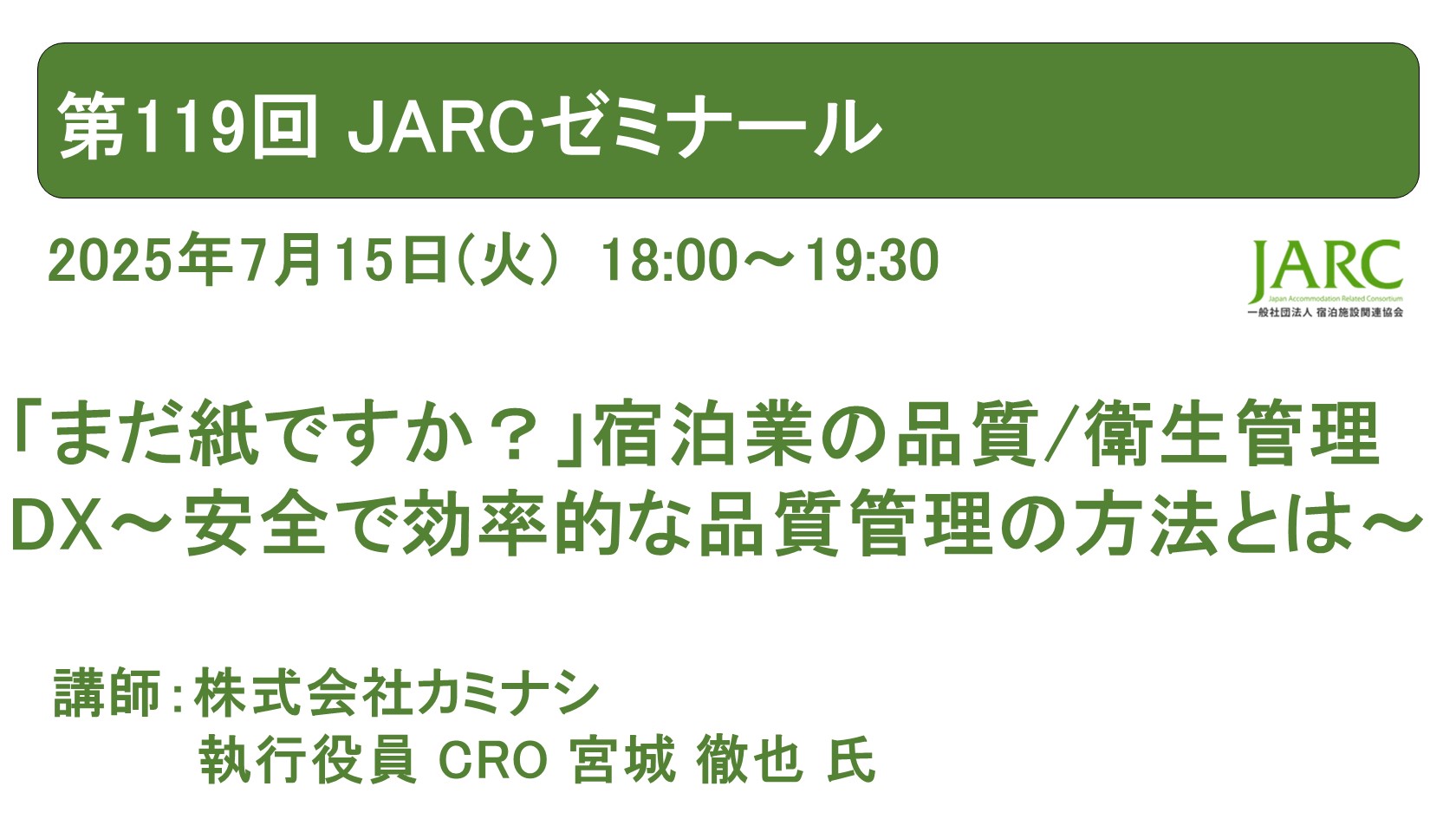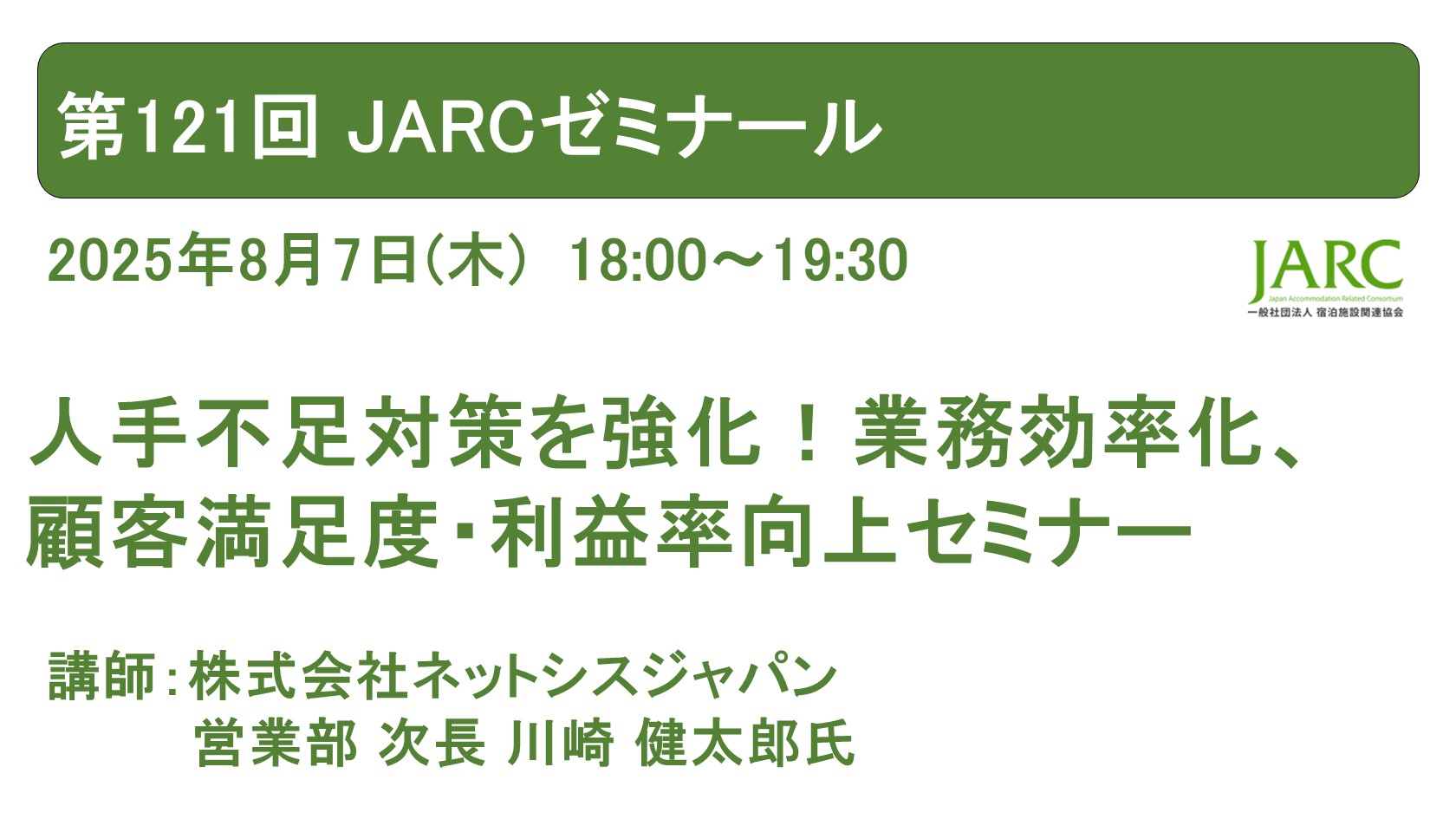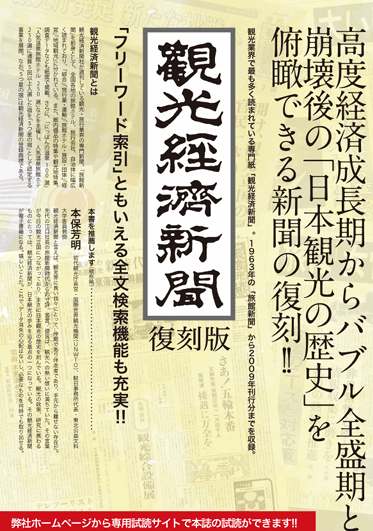「コロナショック」が実体経済に大きな打撃を与えている。先般開かれた政府の専門家会議では、本件に係る国内の損失が16兆円を超えるとの試算も出た。とりわけ急激にインバウンド需要が高まっていた観光産業は受け入れ体制の整備が一部脆弱(ぜいじゃく)だったため、より事態は深刻であるということはご承知の通りだろう。
一方、こうした中であっても業績が堅調な企業は存在する。その多くはインフラ関連であるが、中には労働集約型の小売業やサービス業でありながら、「コロナショック」発生後に業績向上をなしえている企業もある。
それらの企業に共通する特徴は、「生産性の高さ」を追求し続けているという点である。その一例として、首都圏を中心にスーパーマーケットチェーンを展開しているA社は、売上高に対する固定費の比率が、同規模の同業他社と比較して10%近くも低い。
A社では数年前から独自の仕組みを取り入れ、日々の業務(タスク)を「誰が、何を、いつまでに、どのように行う」というレベルまで可視化し、従業員各人の状況に応じて動的に割り振ることで属人的、非効率的な部分を徹底的に廃した。
これによりA社の販売管理費(固定費)は人件費を中心に大きく低下。価格面での競争力を維持しつつ十分な利益を確保することが可能となり、結果、「コロナショック」の中でも盤石な事業構造を作り上げることができたのである。実際、同社の決算説明会資料には「生産性の高さが(A社の)強さ」という言葉が堂々と掲げられている。
イノベーションは市場が危機に直面した時に起こるといわれている。90年代バブル崩壊の時は個人レベルの連絡ツールとして移動体通信分野が台頭した。また、東日本大震災の時はネット通販やロジスティクスが大きく発展する契機となった。そんな中、観光産業は良くも悪くも事業構造をあまり変化させないまま今日までやってきた企業が多いように思える。
「コロナショック」は難敵だ。しかし同時に、観光産業の事業構造を変革させるためのチャンスでもあると私は考えている。
(一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会会員 株式会社マイナビ 西宣秋)