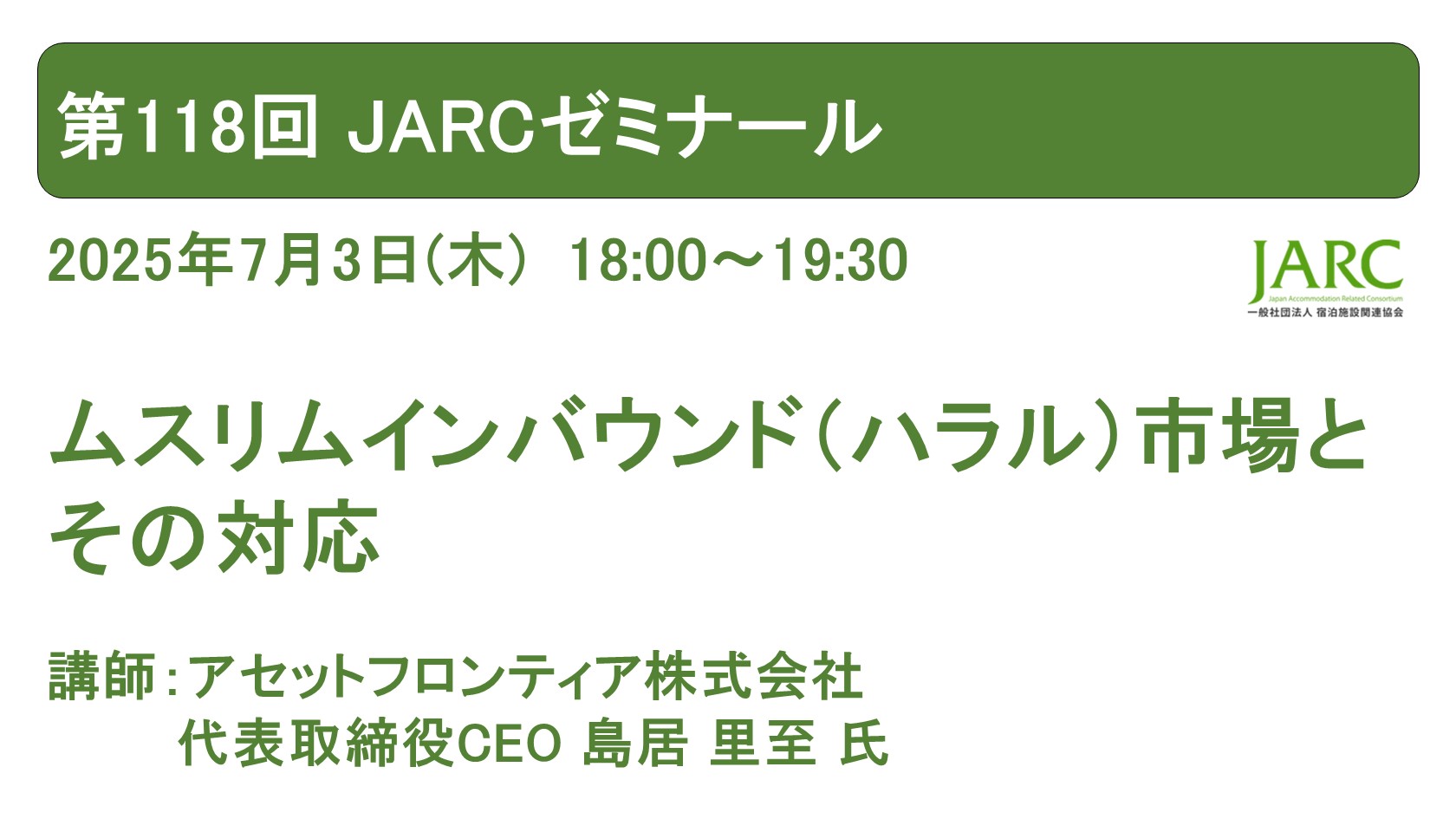11月2日に九州運輸局が主催するシンポジウム「KYUSHU ISLANDS SUMMIT 旅館・ホテル・温泉文化が支える未来」が開催されました。
本シンポジウムは、昨年12月に開催された「女性のための宿泊業オンラインセミナー」の第2弾として企画されており、今回は学園祭開催中の九州産業大学で実施。参加者の多くは学生さんで、宿泊産業に興味を持ってもらうことを目的としています。
とはいえ、観光・地域における宿の存在意義や、温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録を目指す動きを鑑み、「地域の要となる宿とは」「インバウンドのお客さんに選んでもらう宿とは」というテーマが根底にありましたので、宿泊業に従事される皆さんにも参考にしていただけそうです。
観光庁初代長官であり、UN tourism本保芳明代表の基調講演では、訪日客におけるラグジュアリー層の解釈がとても明解で勉強になりました。
その後のパネルディスカッションでは、全旅連の井上善博会長から自然災害時の宿の役割、日本旅館協会の桑野和泉会長からは、保養地としての温泉地・宿づくり、JR九州の浜田真知子執行役員からは、地域と連動する宿づくりが言及され、本保代表も議論にご参加。大変僭越(せんえつ)ながら、私はファシリテーターを務めさせていただきました。
「インバウンドのお客さんに選んでもらう宿とは」という議論では、本保代表が「現在、日本の旅館が世界に伝わっていないのは定義とスタンダードがないから」と明確な答えを導き出されており、パネラーの皆さんも「旅館」の定義を行っていくことに同意されていました。
最後の学生さんからの質問で、宿泊業界への就職に対し不安が示されたことも、非常にリアルでした。YouTubeに動画がアップされていますので、ぜひご覧になってみてください。
現在、ユネスコ推進協議会が掲げる2028年早期に、温泉文化がユネスコ無形文化遺産に登録されるならば、温泉入浴ができる宿泊施設にとって、またとないチャンスが訪れます。そう、日本特有の温泉旅館が世界から注目されるのです。
その時までに、何をすべきなのか―。以下、持論を列記します。
まずプロモーションの強化、インスタ映えする写真の用意、海外の旅行会社やメディアを招致、多言語対応の環境整備は必須です。今から準備しておいた方がいいでしょう。
その上で、外国人が日本特有の旅館(温泉旅館)に宿泊すると何ができ、何を楽しめるのか。それは世界のスタンダードのホテルとどう異なるのか。一定のクオリティーを保った日本の旅館を「ブランド」としてアピールしていく必要があります。
そのためには、未来の「旅館」の在り方について考えを深めていくことが重要です。最初は旅館の皆さんで、後世まで残していくものを見極める。その上でハードとソフト両方で何を改善するか、何を変えないかを考える。
改善点に入れていただきたいのは、お客さんの多様性を受け入れるための食事提供の方法、自然災害を含めたいざという時の対処法、セキュリティーの問題などです。
グローバルチェーンホテルに泊まるのと同等のサービスを意識しつつ、温泉旅館特有の要素(「何を変えないか」に相当します)を明確にするのです。
もちろん大前提として、積極的にインバウンドを取り込んでいくかどうかの判断が大切です。積極的な気持ちがないなら、むしろ国内のお客さんのニーズをしっかりと把握する必要があります。
次回は、先進的な地域と宿の取り組みをご紹介します。
(温泉エッセイスト)

(観光経済新聞2024年12月16日号掲載コラム)